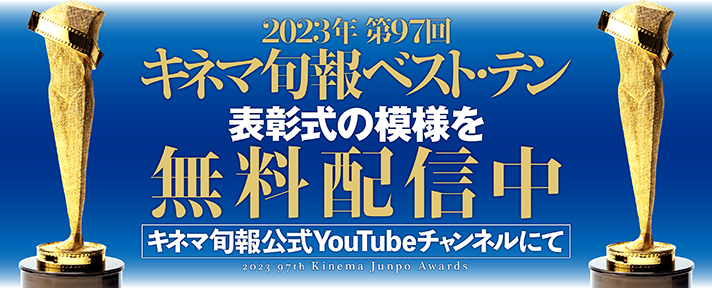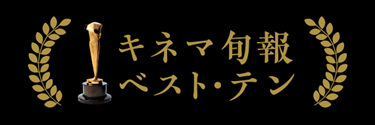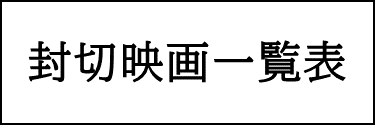「きみ波」が語る『君の名は。』『風立ちぬ』への応答
- 2019年06月30日
「きみ波」が語る『君の名は。』『風立ちぬ』への応答

(c)2019「きみと、波にのれたら」製作委員会
◎6月21日(金)より全国にて
『きみと、波にのれたら』は、まるで水晶のように輝く印象を残す。透明で、澄んでいて、そして脆さを含んだ硬さを感じさせる。
これまでの湯浅政明監督は軟らかく、ダイナミックだった。今回の作品は、硬質で、静的だ。内包する時間感覚も異なる。『マインド・ゲーム』(2004年)や『夜は短し歩けよ乙女』(2017年)のような複線的な時間感覚も、『夜明け告げるルーのうた』(2017年)や『DEVILMAN crybaby』(2018年)のように世代を超えていく超人的なタイムスケールもなく、ただただ、今ここで経過していく時間を描くことに専念している。過去を探ろうとはするが、そこから現在まで時間は一直線に伸びるだけだ。寄り道をしようともせず。
本作の後半にはいかにも湯浅らしい大スペクタクルが展開されるが、それでさえ『マインド・ゲーム』の大脱出劇のように現実のポテンシャルを解放しバラけさせていくようなものではなく、むしろ地に足をつけるためのものである。昇天するべきものを天に昇らせ、まだこの世に残るものは硬い地面へと降ろすための儀式のようなのだ。
『君の名は。』『風立ちぬ』への応答

(c)2019「きみと、波にのれたら」製作委員会
本作は、死の領域を死の領域としてありつづけさせる。そして、そのことによって、自然と近年の二本の長篇アニメを思い出させる。
たとえば、スマートフォンに残るメモリーやデータは、二人の過去を明らかにできること。これは明確に『君の名は。』(2016年)に対する応答である。過去は決して捏造されたり消えたりしないと語るのだ。
また、『風立ちぬ』(2013年)に対する応答に思えるところもある。あの作品で、主人公の二郎は、最愛の人の死後、その死者に「生きて」と語らせる。自らの生に、死を呑みこんでいこうとするわけだ。一方で本作は、物語の終盤に、死者の声を突如として巨大に響かせる。その声が語るのは、「死ぬつもりなどなかった」「生きたかった」という純粋な願いである。死は死としてある。それを、生者は簡単に乗り越えることができない。そう本作は語る。
一度しかない生と時間

(c)2019「きみと、波にのれたら」製作委員会
だから『きみと、波にのれたら』は、とても真っ当なことを語る作品だとも言える―生は生であり、死は死である。いやむしろ、その真っ当さが、極限にまで高められていると言うべきか。プレス資料のインタビューによると、湯浅政明は「ひな子を波にのせてあげたかった」と語っている。本作が本当に驚かせるのは、この発言が、比喩的な意味を含んでいないということだ。ひな子は本当に、ただ波にのるだけなのだ。文字通りに、行為として。
つまり、湯浅は本作で、過去作と異なる新たな実験をしたといえる。それは、一回性のある生・時間を描くことである。その結果、「普通の」生活がキラキラと輝き始める。本作の最も感動的な部分は、「普通の」生活を描く前半―ひな子と港の恋人としての時間にある。愛し合う二人が過ごす、ごく当たり前の時間が、結晶化される。その尊さは、時間やフォルムをグニャリと変質させたりはしない、禁欲的な表現によって初めて可能になる。
湯浅はこれまで、アニメーションの多義的な性質を活用してきた。その性質によって、死を含む雑多なあらゆるものを包括し、呑みこんでしまおうとした。でも、今回はそのやり方に背を向ける。本作の水晶のようなイメージは、硬くて脆い、壊れたら取り返しのつかない私たちの生について語るのだ。
湯浅はそっと、ひな子を波にのせる。繊細な水晶でできたような切なく光り輝くその存在を、やさしく。それを変容させることなど、許されないと言わんばかりに。ただそこに、優しく存在させるだけの映像。本作で湯浅政明はまたしても、アニメーションの最先端を走ってしまった。
文=土居伸彰/制作:キネマ旬報社