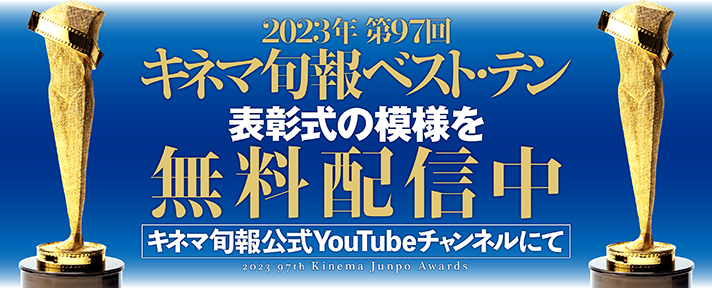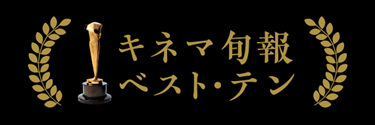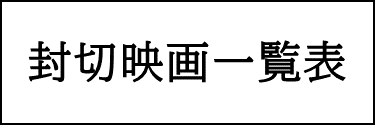竹野内豊・山田孝之W主演。観客を心の原風景へといざなう鬼才の新境地「唄う六人の女」を3つの観点でひも解く

出演者が全てマネキン人形という異色のドラマ『オー!マイキー』、山田孝之が3人のぶっ飛んだキャラクターを怪演した「ミロクローゼ」──シュルレアリスムに音楽劇とコメディを混ぜ合わせ、ヨーロピアンな原色の色遣いに和の要素を盛り込んでくる鬼才・石橋義正監督。映画・パフォーマンスアート・ファッションショー等々、様々なフィールドで活躍する彼の、10年以上の時を経た監督作「唄う六人の女」が10月27日より劇場公開される。
竹野内豊と山田孝之がW主演を務め(山田はプロデュースも兼任)、水川あさみ、アオイヤマダ、服部樹咲、萩原みのり、桃果、武田玲奈といった多彩な面々がふたりを惑わす“女たち”を演じた本作。その魅力を3つの観点でひも解いていきたい。
石橋義正ワールドに加わったシリアス×謎解き要素

冒頭に軽く石橋監督の作風を紹介したが、先に挙げた特徴はほんの一部でしかない。一言でいえば途方もないイマジネーション=世界観で観る者を呑み込んでくるクリエイターだが、本作においては“らしさ”と“新しさ”の両面が確認できる。ベースとなるのは過去作品にもみられる美意識や空気感なのだが、テーマ性やトーンはこれまでとは大きく異なっているのだ。
元々『唄う六人の女』は、石橋が監督を務めたバラエティ番組『ミリオン・プレジャー・ナイト』(2000)のいちコーナーだった。古民家を舞台に、和服の美女が歌を唄ったり楽器を奏でたりする、なかなかにシュールな絵面と独特の雰囲気が特徴的な作品だったが、〈和服〉〈喋らない美女〉〈音楽要素〉〈色遣いやスタイリング〉等の要素は、映画「唄う六人の女」にも色濃く受け継がれている。
ただ、前者が明るめなファンタジーであるのに対し、映画「唄う六人の女」はミステリーやサスペンス、幻想怪奇譚的な雰囲気が強められている。40年以上会っていない父が亡くなり、遺された山を売るために生家に戻った萱島(竹野内豊)と、売買を請け負う開発業者の下請け・宇和島(山田孝之)が事故に遭い、目が覚めると手を縛られ、何も話さない謎めいた女たちに監禁されていた──というのが序盤の展開で、「女たちの正体は?」「父はなぜこの山を遺した?」「宇和島の目的は?」といった謎が、徐々に明かされていく。
萱島の脳裏にフラッシュバックする過去の記憶や、虫を食べたり自在に泳いだりする女たちが匂わす特異性、「砂の女」的なエッセンスなど様々なヒントがちりばめられており、観客が考察をしながら物語を追いかけていく要素が加わった。そうした意味では、石橋監督の作品の中で最もストーリー軸が強固に練られているといえるだろう。
現実感=緊迫感を担保する竹野内豊×山田孝之の芝居

ただ、サスペンスやミステリーといった新要素が、石橋監督が本来持っているエッセンスを薄めるかたちにはなっていない。すなわち、現実世界の理とは一線を画すファンタジー要素だ。サスペンスやミステリー、或いはホラーといったジャンルは観客を没入させられるか否かが特に重要で、そのためには〈なんでもあり〉なファンタジーであっても、ある程度現実に即したルールを設けなければならない(例えば、人は死んだら生き返らない等)。そうした処理を行わないと、観客が推理したり考察したりする楽しみが生まれづらいからだ。
ある種の“縛り”を課すことで、物語と観客の接地面を増やし、距離感を近づけていく。それがエンタメ性につながっていくわけだが、前述した世界観の独自性(アート性)を保つためには、これがなかなか難しいところ。特に、石橋作品のように個性が際立つタイプであればなおさらだ。だが本作においては、ふたつの方法論を組み合わせて解決している。
ひとつは、〈現実から“異界”に迷い込み、何もかもわからない〉という状態。萱島や宇和島が生きる現実社会を冒頭に提示しておいて、彼らが混乱しながら“女たち”や“村”の正体を探っていこうとする展開を敷き、常に現実感VSファンタジー性の構造を崩さない。萱島の恋人かすみ(武田玲奈)が行方不明になった彼を捜す──という物語も並行して描かれ、元の世界に戻れるのか?といった要素を加味しているのが上手い。

そして、俳優陣の芝居。言葉を発さず、超然とした雰囲気を醸し出し続ける女優陣の不変の“妖しさ”に対し、驚いたり不安になったり果ては狂ったり/受け入れたりと、刻一刻と変化する竹野内&山田の芝居のコントラストが鮮烈だ。サスペンスに必須な緊迫感をふたりが生々しく表現し、極限状態で成長していく萱島(竹野内)と発狂していく宇和島(山田)との“対比”が、作品全体にダイナミズムを生み出してもいる。同じ窮地に陥った二人の男の相克──「太平洋の奇跡―フォックスと呼ばれた男―」以来、約11年ぶりの共演となった竹野内と山田のパフォーマンスも、大きな見どころといえよう。
時代とリンクした自然との共生というメッセージ

個性を出しつつ新たな挑戦も行い、エンタメ性にも目を配る本作。ただ観賞後に観客の胸に残るのは、そればかりではないはず。石橋監督が本作に込めた、メッセージ性だ。最後の項目ではネタバレに注意しつつ、本作のテーマについて軽く紹介したい。
本作は、“自然”が一つの主人公になっている。環境保全のため、普段はなかなか撮影が許されない京都の芦生(あしう)の森ほか、手つかずの自然の中に身を置き、作り上げた本作には、随所に自然に対する畏敬の念が感じられる。自然と共生する父と距離を取って都会でコマーシャルフォトグラファーをしていた萱島が、生家に戻る=自然に帰っていき、慈しむようになるのに対し、自然を破壊して利益を得ようとする宇和島がどんどん敵役=ヴィラン的な立ち位置になっていくのも明快で、最終的な出口としてだけではなくテーマ性が全てのシーンにしっかりと乗っている。
また、これはある種の奇縁でもあるが──〈自然との共生〉を今一度見直すことは、我々にとっても関心事のひとつといえるのではないか。コロナ禍におけるソロキャンプやサウナ熱の高まり、地方移住といった自然回帰願望もそうだし、各企業のSDGsへの取り組みや、地球沸騰化が叫ばれるいま、自然とのかかわりを見直すことが急務となっている今日……。そうした時代性も、本作に味方しているように感じられる。
ある種の寓話性を、伝承的なエッセンスも含めて描くことで、日本人の心に訴えかける──。映画が娯楽はもちろん“気づき”を与えるメディアであることを、「唄う六人の女」は再認識させてくれる。
文=SYO 制作=キネマ旬報社
「唄う六人の女」

10月27日(金)よりTOHOシネマズ日比谷ほか全国公開
監督・脚本・編集:石橋義正
脚本:大谷洋介
音楽:加藤賢二、坂本秀一
主題歌:NAQT VANE「NIGHTINGALE」(avex trax)
出演:竹野内豊、山田孝之、水川あさみ、アオイヤマダ、服部樹咲、萩原みのり、桃果、武田玲奈、大西信満、植木祥平、下京慶子、鈴木聖奈、津田寛治、白川和子、竹中直人
配給:ナカチカピクチャーズ、パルコ
©2023「唄う六人の女」製作委員会
公式HP:https://www.six-singing-women.jp