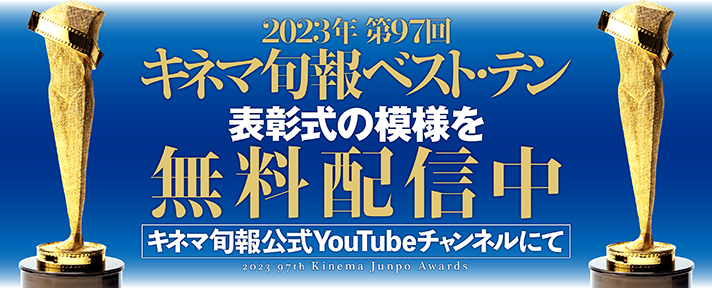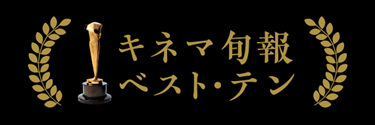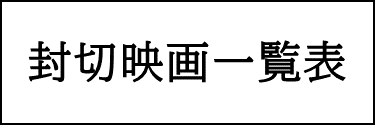エリザベート 1878の映画専門家レビュー一覧
エリザベート 1878
19世紀にヨーロッパ宮廷一の美貌と謳われたオーストリア皇妃エリザベートが40歳を迎えた姿を「オールド」のヴィッキー・クリープス主演で描いた歴史劇。厳格な公務をますます窮屈に思うエリザベートは、世間の理想像から自由になるため、ある計画を思いつく。前作「Der Boden unter den Fusen」(原題)が2019年第69回ベルリン国際映画祭コンペティション部門で上映されたマリー・クロイツァー監督が、史実に捉われない大胆な表現でシシィの愛称で親しまれる伝説的皇妃の素顔を浮き彫りにする。エリザベートを演じたヴィッキー・クリープスは本作により2022年第75回カンヌ国際映画祭ある視点部門最優秀演技賞を受賞。2023年第95回アカデミー賞国際長編映画賞オーストリア代表作品。
-
映画監督
清原惟
すべてのシーンに細やかさが行き届いている。派手なことはしないけど、一つひとつに含みを持った丁寧な脚本。女性として生きることの苦しみや寂しさが伝わってきて息が詰まりそうになる一方で、ひとりの人間として自分自身として生きようとする彼女のものだけの時間が輝いていた。お風呂で息を止める記録を更新したり、真夜中の湖でいとこと泳いだり、さまざまな水のシーンの描写が印象的。突如ストーンズの曲がハープの演奏で流れてくるのも、不思議と違和感がなくて面白かった。
-
編集者、映画批評家
高崎俊夫
ロミー・シュナイダーの出世作「プリンセス・シシー」で人口に膾炙した皇妃エリザベートの生涯を気鋭の女性監督が現代的なフェミニズムの視点で脱=神話化した大胆不敵な試みだ。冒頭から頻出するコルセットを締めるシーンがある種の拷問として描かれるのが印象的。時代考証も無視してあり得たかもしれない歴史的な真実を幻視する語り口には、数多の抑圧と禁制によって拘束されたヒロインを「舞踏会の手帖」よろしき幻滅に満ちた流浪の遍歴から救抜しようとする作り手の意思が垣間見える。
-
映画批評・編集
渡部幻
皇妃“シシー”といえば、まだ幼さの残るロミー・シュナイダーが演じた2つのシシー、おてんば娘の絵本の如し「3部作」とヴィスコンティの重厚な「ルートヴィヒ」をまず思い出すが、この新作は全く異なる物語を提出する。40歳迎えてなお身長172cmにウエスト51センチ、体重40キロ台を維持して「美貌が衰えて暗い雲のようになる」ことをおそれる不安と性の寂しさ。惨めに描いているのではない。クリープスは新たな解釈を加えてエリザベート像を解き放った。それだけに助演者の魅力不足が残念。
1 -
3件表示/全3件