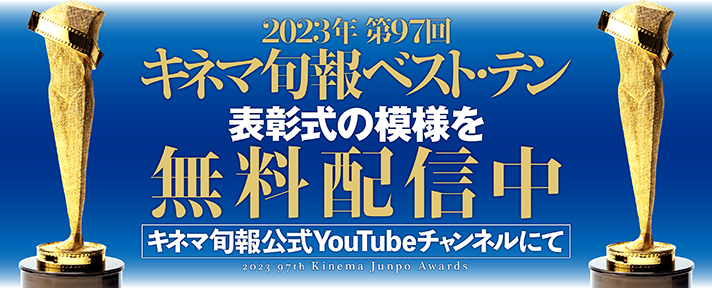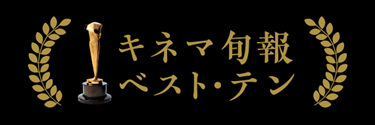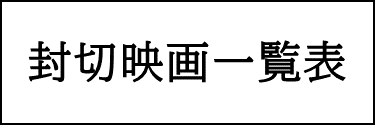暴力をめぐる対話の映画専門家レビュー一覧
-
映画監督/脚本家
いまおかしんじ
よくこれだけの映像を集めてきたと思う。生々しい暴力描写を延々と写し続ける。居丈高な警官たちが超ムカつく。怒りで体が震える。ホント最低! やられた人たちや擁護している人たちの話だけじゃなくて、警察関係者も発言しているのが良かった。でもやはりと思う。これでは警察が圧倒的に悪者だ。もちろん悪いんだけど。複雑な気持ちになる。映像を切り取るとどんなふうにでも解釈できる。途中で喋っていた風格のメチャクチャあるおばさんが良かった。頭がいいってこういうこと。
-
文筆家/女優
唾蓮みどり
パリで起きた黄色いベストを身につけた市民によるデモと、市民に警察が向ける武器。銃を向けることはもとより暴力は簡単に人間から言葉を奪う。向けられた銃を前に対話は成立するのか。スマートフォン撮影をはじめとした数々の暴動の映像を前に、意味や考察、反論などの言葉が付け加えられていく。特に作家のアラン・ダマジオが「誰かを“暴力的だ”と指摘する正当性を誰が持っているのか」という言葉が残った。“暴力的”なのではなく“暴力そのもの”が映し出される意味を考える。
-
映画批評家、東京都立大助教
須藤健太郎
ラストショットをどう捉えるべきか。批判を見越したものと思うが、私にはやはり許容しがたい。映されている内容がおぞましいからではない。この直視しがたい映像があたかも結論であるかのように最後に置かれているからだ(このラストへの伏線が作中に仕込まれているためそう見ざるをえない)。この映画は対話であると同時に映像の分析であり、そういう言葉の力に賭けられているように見えた。だが、最後に見せられるのは見る者をただ絶句させる、極めつけのスペクタクルではないか。
1 -
3件表示/全3件