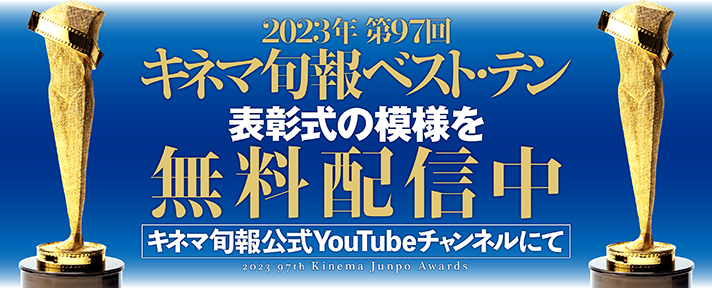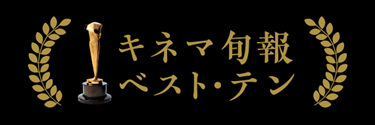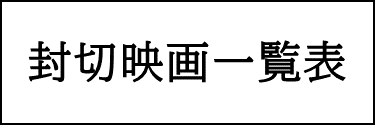映画専門家レビュー一覧
-
PLAY! 勝つとか負けるとかは、どーでもよくて
-
文筆家
和泉萌香
今回のレビュー4作品はどれも都心部から離れた土地が舞台で、本作は徳島の港町を舞台に、自転車に乗った高校生たちが爽やかに海のそばを駆け抜ける。勝ち負けではなく、得手不得手、できるできない、自分の力ではどうにもならないことがたくさん溢れている世界に生きる少年たちが、互いには干渉しすぎることなくたった一つのことに取り組む姿の描写に加え、eスポーツ会社の大人たちが語るメッセージは、子ども時代を子どもとして過ごさせる優しさに溢れている。
-
フランス文学者
谷昌親
観る前は、eスポーツがテーマで映画としてどれだけ成り立つのかと不安視していたが、なかなか見ごたえのある作品になっている。青春映画で力を発揮する古厩監督の演出のたまものであることはまちがいないが、実話の映画化というこの作品で、主要な人物となる高専生3人の絶妙のバランス、そしてなによりも彼らが生活の場としている徳島の風景が魅力的だ。少年たちがそれぞれに問題を抱えながら過ごす日々が、海辺にある小さな町の風景のなかでこそ生き生きとしたものになっていく。
-
映画評論家
吉田広明
優秀だがいつも一人で行動する三年生と、金髪で一見チャラ男だが心優しい二年生を中心に、「仲間」となった彼らがeスポーツに臨む。部活ものの定番ではあるが、個性がバラバラな三人がまとまってゆく過程の背後に、容易に片付かないそれぞれの家庭が抱える問題や、外国人、障害者など多様な参加者たちの描写をさりげなく挟んで世界に奥行きを与え、決して説明的にならず、しかし紋切り型の友情物語、スポーツ物語の多幸的終局を控える慎ましさが好ましい。さすがベテラン監督。
-
-
DOGMAN ドッグマン
-
翻訳者、映画批評
篠儀直子
情報ゼロの状態で観始めて、ベタとキッチュが混ざった雰囲気に困惑しつつ観ていたら、監督がリュック・ベッソンだと最後にわかってなぜか納得。異常な成育環境のなかで犬と特殊な関係を結ぶだけでなく、演劇に魅せられたり、異性装の歌姫として人気を博したりしつつ、一貫して神の存在に憑かれている主人公の物語は盛りこみすぎな気もするが、はぐれ者や異常性格の役でいまや地位を確立した感のある(?)C・L・ジョーンズに不思議な魅力がある。あと、わんこ好きは観るといいのかも。
-
編集者/東北芸術工科大学教授
菅付雅信
父親から虐待を受けて犬小屋で育った男がドッグトレーナーとなり、女装してドラァグクィーンとしての活動と訓練された犬を使った盗みを生業とする中で、犯罪組織に目をつけられてしまう。リュック・ベッソンの脚本・監督によるこの犯罪映画は、彼の持つ美学性とバイオレンス性が久々に幸福な結婚をした快作。主演ケイレブ・ランドリー・ジョーンズのブチ切れた怪演も相まって、「ああ、ベッソンが帰ってきた」と嬉しくなる。ただ、悪役があまりに弱く、それほどハラハラしないのが玉にキズ。
-
俳優、映画監督、プロデューサー
杉野希妃
黒人の精神科医が聞き手となり、10数匹もの犬と生活するダグラスの半生を辿る。犬小屋に数年間閉じ込められ、下半身不随となった虐待サバイバーであるダグラスの生い立ちがあまりに壮絶。後半、犬を使って犯罪に手を染めるナンセンスな飛躍に戸惑いつつも、賢い犬たちを愛でながらの鑑賞は私のような愛犬家にはたまらない。犬やドラァグクイーンなど、出てくるモチーフすべてがビジュアル先行に思えて、深みを感じられず。気怠く熱演するケイレブの色気が作品に重厚感を与えている。
-
-
愛のゆくえ
-
ライター、編集
岡本敦史
雪国のシビアな思春期ドラマとして始まったかと思えば、大島弓子の漫画『快速帆船』を思わせる展開になり、映画の質感が変幻していくところは面白い。少女の彷徨を幻想的に描く手つきは相米慎二っぽくもある。ただ、一つひとつのセグメントが撫でる程度で通りすぎていくので(特に後半以降)、漠然とした印象が終盤にかけて膨らみがち。監督の自伝的要素が色濃いそうだが、内省を突破する力強さも示してほしかった。主演の長澤樹のインパクトに対し、作品自体の力がもう少し届かない。
-
映画評論家
北川れい子
重量感のある北海道の雪深い風景が、大都会で自ら迷子になった少女の支えになっている。自分はまだやっと片足が生えたばかりのおたまじゃくしだ、と呟くもどかしい14歳。雪国生まれの彼女が、母親の死で東京に住む父親に引きとられ、そこから逃げ出してのリアルな体験。その体験には、聖と俗、死、悪意と優しさ、アートに歴史とてんこ盛り、さらに故郷まで続く三途の川?まで登場する。いくつかパターン通りの場面もあるが、幻想をリアル化する宮嶋監督のセンスは素晴らしい。
-
映画評論家
吉田伊知郎
新人監督らしい直情的でひたむきな作りには惹かれるが、類型的な設定や台詞に没入を阻害される。悪意の描写も図式的すぎる。監督自身の実体験が多く反映されているようだが、それを客観視する力があれば爆発的な傑作になっていた予感が漂う。終盤の非現実的な飛躍は魅せるものがあるだけに、そこへ至るまでの北海道の雪の冷たさや都会の孤独感の描写にこそ注力してほしかった。長澤樹の無表情は映画を象徴させる力があるだけに、もっと生かせるはず。魅力的な細部が零れ落ちている。
-
-
水平線(2023)
-
文筆家
和泉萌香
冒頭、ラジオが流れる走行シーンに思わず佐向大「夜を走る」を想起。撮影も同じ渡邉寿岳によるもので、夜から朝にかけての船上からの眺め、暗闇に揺らめく青い灯りなどをとらえるカメラが凜として素晴らしい。「夜を走る」は死体を出発点に男たちの物語が動き出すが、本作は不在を中心に男の車が悲しくもぐるぐるとさまよう。が、悪徳ジャーナリストやスナックに通う父親=主人公と台詞含め男性登場人物たちが、肝心の不在以上の虚しさと共に紋切り型かつ簡略化されているようにも。
-
フランス文学者
谷昌親
散骨業を営む真吾という男の物語で、彼は福島の海辺の町に住む元漁師であり、身近な存在を津波で海にさらわれている。これだけでも充分に複雑な境遇だが、その真吾のそれなりに穏やかな日々を乱すような事件が起きるのだ。なかなか重厚なテーマを、これが初メガホンの小林且弥監督が力強く演出し、俳優陣もそれに応えている。それぞれのシーンは観客の胸に迫るものがあるはずだ。しかし、個々のシーンが突出しすぎるのか、シーンとシーンが有機的に結びついていかないのが惜しまれる。
-
映画評論家
吉田広明
なぜ主人公が散骨業を営んでいるのか、通り魔殺人犯の遺骨を巡ってのジャーナリスト、娘らとの確執からその理由が明らかになってゆく。何より、ごく普通のおっさんが倫理的問題にいかに処するか、その決意を淡々と描写を積み重ねて説得的に描いており、おっさんがカッコよく見えてくる。散骨に至る理由は、残された者(殺人犯遺族のみならず自分たち父娘含め)の未来のためではあるが、誰であれ鎮魂はされるべきではという観点まで突き詰めれば宗教的次元まで行けたのだがとは思う。
-
-
52ヘルツのクジラたち
-
文筆家
和泉萌香
原作は未読。義父と母親からの虐待を受けていた女性が主人公だが、彼女を世界の中心に次から次へと人物が登場。最低最悪の素顔に皮をかぶったボンボンのキャラクターはさておき、児童虐待の被害者である少年と出会ってからも、それをしちゃダメだろうという彼女の行動が気になりひとりよがりにも思えてしまう。彼女に手をさしのべる彼に対しての物語の仕打ちも酷すぎるもので(女友だちも優しすぎない?)きれいな海が広がるなか、感動的に集束していくさまを見てもまったく納得できず。
-
フランス文学者
谷昌親
虐待の被害者で、しかもヤングケアラーだったというヒロインをはじめとして、社会に自分らしい居場所を見つけられない人物が何人も出てくる。だからこそ感動的な物語でもあるのだし、ヒロインの貴湖を演じた杉咲花にとって代表作にもなるだろう。すでに大ベテランと言ってもいい成島出監督の演出も手堅い。だが、これでもかこれでもかと続いていく、重たく、それだけに人の心を打たずにはおかないエピソードの積み重ねが、逆に作品を薄っぺらなものにしていると感じさせるのが皮肉だ。
-
映画評論家
吉田広明
児童虐待にヤングケアラー、ネグレクトにトランスジェンダーと、どれ一つとってもまともに扱えば血の出る家族や性を巡る問題を次から次と渡り歩いて、その一つとして掘り下げることなく、大映テレビドラマ顔負けのエゲツなく不自然極まる展開で見る者の感情を引きずり回すことにばかり腐心している。これで感動作の積もりだから恐れ入る。マイノリティ問題を飯の種にするなとは言わない。しかしこれは共感の皮を被った搾取であり、真摯にそれに取り組む人へのほとんど侮辱である。
-
-
コットンテール
-
文筆業
奈々村久生
「ぐるりのこと。」の夫婦コンビふたたび。イギリス出身の監督が日本的な家族関係や精神性を再現する試みかと思いきや、物語や登場人物像そのものが監督自身を形成した実体験に深く基づいており、自分の世界観を追求することで必然的に日本的な描写も強化される。その意味で日本映画といっても遜色ない完成度には達している。同時に、リリー・フランキーが体現するある種の日本的な男性像は、当然のごとく女性を美化しすぎているが、それを破壊する木村多江の変貌が見事だった。
-
アダルトビデオ監督
二村ヒトシ
奇妙な味わいの映画。その奇妙さが監督の持ち味か、英語で書かれたセリフを日本語に訳して日本人の俳優が演じるからなのか、日本人が演じる日本の家族を東京と英国の田舎でのロケで英国人が演出してるからなのかはわからないが、いやな奇妙さではない。万国共通〈愛する相手が本当に欲しいものを言葉にしてるのに、そのままの意味で聴きとることができない男が勝手に感じてる孤独〉の問題。しかしこの問題はなんで万国共通なんだろうな。と万国の男性が自分をかえりみて頭をかかえる。
-
映画評論家
真魚八重子
この映画は“家族再生を描いた”と銘打たれているが、逆に家族間のぎくしゃくとした不仲が明瞭になる作品という印象だ。リリー・フランキーが妻を深く愛していることの表現として、彼の頑固で融通の利かない性格が前面に出される。妻の遺灰をイギリスへ撒きにいく旅も、用意周到な息子にたてついて、フランキーは路線図も読めぬ土地で猪突猛進していく。それが愛ゆえというのは独りよがりで、結局誰にとっても徒労となる。筆者の父も同類だったので、生前の振り回された疲労を思い出してしまった。
-
-
FEAST 狂宴
-
映画監督
清原惟
交通事故で夫を亡くした女性が、事故を起こした相手の家族が経営するレストランで働く物語。交通事故で轢いてしまっただけならともかく、その場で助けずひき逃げをしてしまう男たちが、数年の服役(しかも父が肩代わり)によって許されることをハッピーエンドとして描くのは、文化の違いによる倫理観の違いはあるにしても、さすがに理解が難しいものだった。罪の意識が描かれるが、それも教会で懺悔して終わりというお気楽さで、夫をひき逃げした人の店で働く心情も全然わからない。
-
編集者、映画批評家
高崎俊夫
メキシコ時代のブニュエルのメロドラマに似た感触がある。交通事故を起こした大富豪の加害者と貧しい被害者という非対称的な構図、さらに父親は息子の身代わりで刑務所に入り、被害者一家は加害者の大邸宅で使用人として働き、事なきを得る。罪過ではなく赦しという絵に描いた善意が瀰漫する日常の水面下で残忍な復讐劇が勃発するという予見(期待?)は裏切られる。クリシェと化してしまった因果律的なドラマツルギーへの異議申し立て、確信犯的な結末というべきか。
-