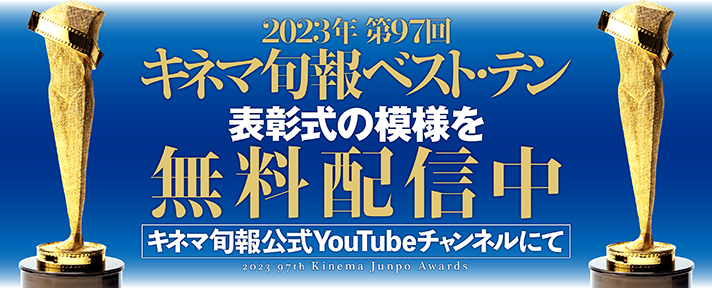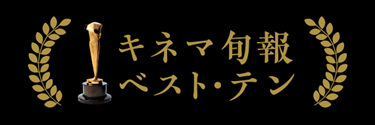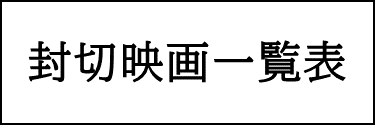母の聖戦の映画専門家レビュー一覧
母の聖戦
年間推定6万件の誘拐ビジネスが横行するメキシコを舞台にした実話ベースの社会派クライム・スリラー。犯罪組織に誘拐された愛娘の奪還を誓う母親の深い愛情と執念の闘争が描かれる。ルーマニア生まれでベルギーを拠点に活動するテオドラ・アナ・ミハイ監督が理不尽な暴力が渦巻く世界を変えたいと企画、本作で劇映画デビューした。「ある子供」のジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ兄弟、「4ヶ月、3週と2日」のクリスティアン・ムンジウ、「或る終焉」のミシェル・フランコといったカンヌ受賞監督たちがプロデュース。第74回カンヌ国際映画祭ある視点部門で勇気賞を受賞、第34回東京国際映画祭コンペティション部門では「市民」のタイトルで上映され、審査委員特別賞を受賞した。
-
映画監督/脚本家
いまおかしんじ
メキシコの何気ない街の風景が怖い。車の荷台に乗っている軍人の銃が怖い。母が目をひん?いて街をさまよう。車の中からのショットが不安を煽る。優柔不断な夫は自分のことしか考えていない。金だけ取られて娘は帰ってこない。物語はどんどん予想を裏切っていく。手を組んだ軍人も胡散臭い。誰も頼れない。自分でやるしかない。彼女がカバンからピストルを取り出したときにはドキッとした。撃たないでくれと祈る。母の聖戦は孤独だ。どこにもたどり着かない。胸が苦しい。
-
文筆家/俳優
睡蓮みどり
母は強し、とか、女は強いとか、そういう言葉をこの映画に対して絶対に使いたくないと思った。自分の娘が生きているのかさえわからない状態で、それでも生きていかなければならない。自分が生きていなければ娘を見つけ出すことは絶対にできないからだ。危険のなかに自らずんずんと突き進む、生きる覚悟が焼き付けられている。ここにあるのは怒りの共闘だ。モデルになった女性の話から、これを映画にしなければと思った監督の使命感を、強い光を宿した母シエロの瞳から感じ取る。
-
映画批評家、都立大助教
須藤健太郎
原題は「市民」。その邦題が、なぜ宗教的な概念である「聖戦」になってしまうのか。しかも、「聖戦」といえばいまではイスラームにおけるジハードをすぐさま想起させる単語でもある。この映画は、警察でも軍人でもない、ましてやマフィアでもない民間の一般人の女性が誘拐された娘を探すために奔走するという話なので、邦題は内容にそぐわない。「母」はともかく、メキシコが舞台なのにどうして「聖戦」なんて言葉が浮かんだのか。この一語でどういう観客層に届くのかを考えてみる。
1 -
3件表示/全3件