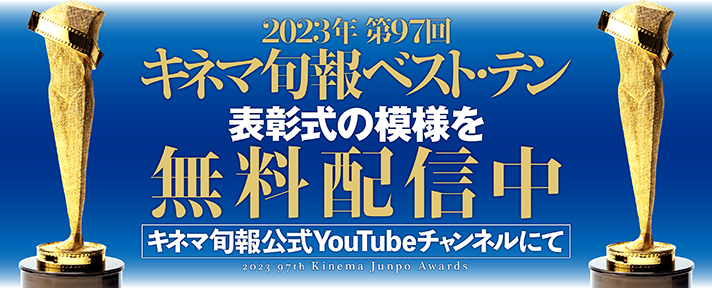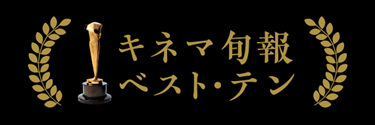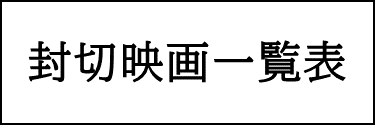アトランティス(2019)の映画専門家レビュー一覧
アトランティス(2019)
「ザ・トライブ」に製作・撮影・編集で参加したウクライナの俊英ヴァレンチン・ヴァシャノヴィチの監督作。ロシアとの戦争終結から1年後の2025年。戦争で家族や友人を失った青年セルヒーは、ボランティアの女性と出会い、“生きる”意味を見つめる。出演は「リフレクション」のアンドリー・リマルーク。2019年の東京国際映画祭で審査員特別賞を受賞している。
-
米文学・文化研究
冨塚亮平
撮影・編集を兼務する監督のこだわりが隅々まで行き届いた、ワンシーンワンカットで距離を置いた対象をしばしば正面から捉える画面構成は、美的な意図と共に、直視し難い光景を観客の目に焼きつけるために選ばれた方法だろう。加えて、二度現れるサーモグラフィーを用いた場面では、赤外線が示す色の視覚的変化を通して、悲惨な状況をドキュメンタリー風に切り取る科学的で即物的な視線と、それでもこの場所で生き続けようとする主人公の微かな希望とが、見事に交差させられている。
-
日本未公開映画上映・配給団体Gucchi's Free School主宰
降矢聡
固定カメラかつワンシーンワンカットで基本構成される画面作りと同じく、語られることも極めてシンプルで力強い。登場人物は皆、延々と作業する者、あるいは作業まで待機する者である。画面には彼らにはどうしようもないほど巨大なスケールのものが常に映り込んでいる。彼らの作業とは、戦後の土地や亡くなった兵士たちの処理だ。その作業と待機の時間をカットを割って省略、効率的に描くことを厳しく禁じる本作は、私たちに戦争のあとに残る途方もなさをただただ伝えている。
-
文筆業
八幡橙
定点から一定の距離を保って静かに対象を見つめる長回しのカメラ。その目が見つめるのは、あちこちに地雷が埋められ、そこここに死体が転がり、かつてその場に豊かな暮らしがあったことが信じられないほど灰にまみれた誰もいない家々が点在するウクライナの姿だ。現実の「今」と、ロシアとの戦争終結一年後とされる2025年という時代設定の重なりが加速させる悲痛よ。遺体を回収する女性が語った言葉や、生と死が如実に交錯する終局のシーンに、未来へ繋ぐ思いが仄かに見える。
1 -
3件表示/全3件