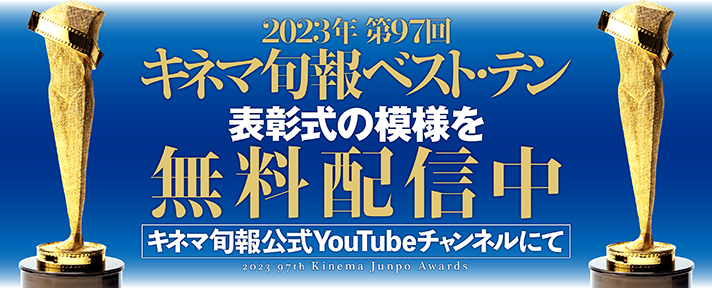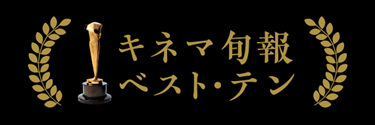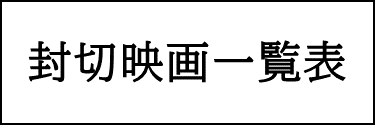ドヴラートフ レニングラードの作家たちの映画専門家レビュー一覧
ドヴラートフ レニングラードの作家たち
現代ロシアの伝説的作家セルゲイ・ドヴラートフの知られざる6日間に迫る、ベルリン映画祭銀熊賞受賞作。1971年レニングラード。詩人ヨシフ・ブロツキーと共に自らの作品を発表しようと模索するドヴラートフだが、政府からの抑圧により出版を封じられてしまう。ドヴラートフを演じるのは、セルビア人俳優のミラン・マリッチ。監督は「神々のたそがれ」のアレクセイ・ゲルマンを父に持つアレクセイ・ゲルマン・ジュニア。4月25日より公開延期。
-
映画評論家
小野寺系
自由な精神を持っているからこそ、誠実だからこそ失墜していく。セルゲイ・ドヴラートフは亡命し成功を収めたが、その一方、祖国で腐っていった才能がどれほどいたのかをうったえかけている熱い作品だ。空気遠近法によるショットが主人公を取り巻く凍てついた環境を表現。破棄された原稿が無残にばらまかれた中を歩く象徴的なシーンは、テオ・アンゲロプロス作品を想起させる深刻な美しさを放つ。同じように閉塞的な社会で、ものを書いている端くれとしても共感させられる。
-
映画評論家
きさらぎ尚
“そこ、大事”的に言えば、主人公のドヴラートフは、例えばソルジェニーツィンやサハロフらの反体制知識人ではないということ。政治的な主張をもって国の体制を批判する訳ではなく、作家同盟の会員でもない彼が、自分の書きたいものを書いて作家になる道を模索する物語は、よってすっと入ってくる。ほんの少し主義を曲げて体制が求めているものを書けばいいのに、それができないドヴラートフの不器用さに共感する。主人公の姿は私たちかも……、が頭をかすめる。映像が美しい。
-
映画監督、脚本家
城定秀夫
「ロシアの伝説的作家ドヴラートフの希望と共に生きた6日間を切り取る」と、チラシにあるが、この6日間というのが、なぜにそこを切り取るんだ……と言いたくなるほど地味で、ドヴラートフとその仲間たちがウダウダ愚痴を言うばかりのほとんど何も起こらない物語が寒々としたロシアの空気を見事に捉えた絶品の画の中で粛々と進んでゆき、この枯淡の味わいが終盤にはクセになってくるとはいえ、ドヴラートフの偉大さは最後までまったく伝わってこないという、なんかヘンな伝記映画。
1 -
3件表示/全3件