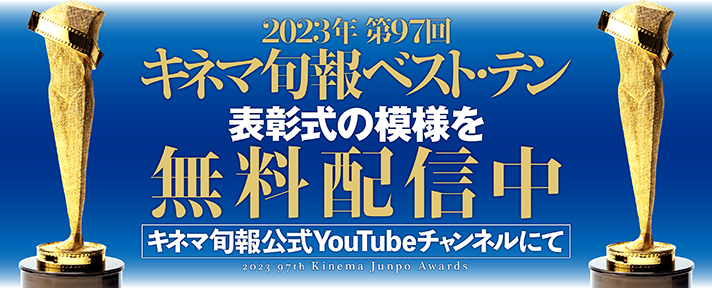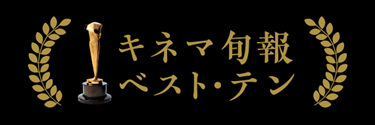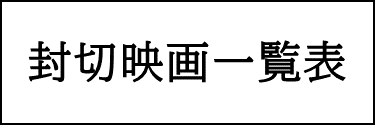「この世界の片隅に」の片渕須直監督が、ウクライナ戦禍の惨状を生々しく伝える映画「マリウポリ 7 日間の記録」を語る
- マンタス・クヴェダラヴィチウス , ウクライナ , 片渕須直 , ロシア , ウクライナ侵攻 , マリウポリ , マリウポリ 7 日間の記録
- 2023年07月30日

約1年半が経つも、いまだに続くロシアのウクライナ侵攻。その戦禍の惨状をありのままに伝えるドキュメンタリー「マリウポリ 7 日間の記録」は、2023年4月15日に公開されてから全国各地で上映が続いている。7月29日にはキネマ旬報シアター(千葉・柏)で上映され、上映後には「この世界の片隅に」の片渕須直監督によるトークショーが行われた。
「この世界の片隅に」では、第二次世界大戦中に戦況が悪化し大切なものが奪われていく日本で、前を向き日々の暮らしを愛おしみながら生きていく主人公すずを描いた片渕監督。現在進行形で起こっているウクライナ侵攻を映した本作をどのように捉えたのか?
監督の遺志を引き継ぎ、この映像を何とかして届けたいという思いを感じた

──まずこの映画をご覧になられた率直な感想は?
「この世界の片隅に」では、戦争中の市民生活がいかに損なわれていくかということを中心に描いたんですが、こうやってドキュメンタリーで観ると、壊れてしまったものはもう日常ではないんだなという気持ちが押し寄せてきました。日常というものは彼らの前から消えてしまって、そこで生活はしているんだけど、それが戻るべき家がある日常とは違っていて、安らぐこともできない、宙ぶらりんにされてしまった時間が続いていて、そういう中にいる辛さが湧き上がってきました。
──スマホで撮影され、ナレーションもなく、家が破壊され教会の中に避難している状況が淡々と描かれているが
マンタス・クヴェダラヴィチウス監督は撮影8日目ぐらいに親ロシア分離派勢力に拘束され、撃たれて殺害されました。撃たれてしまった理由は、マンタス監督にあざがあったため、小銃を撃った際の衝撃でできた痕と思われ、狙撃兵と疑われてしまい殺されてしまったと言われています。そして、助監督であったフィアンセらが遺体と撮影素材のスマホをロシア領内を通って運んでいく。スマホは絶対に見つからないように車の内張りの奥に隠して持ち帰ってきたようです。
そのスマホにあった映像をスタッフが編集している。僕の目からみると、音っていうのはカットとカットの間がブツっと切れちゃうのですが、それが切れて聞こえないように、物凄く巧みに音の配置をやり直してあって、それが一つの時間の流れ、一つの場所っていうのを表す作品として出来上がっているのだなと思いました。
編集というところでも、観客の小さな視点から誘導していって、だんだん大きなものに視点を拡げていく、教会の全体像やここがマリウポリということも、途中で教会の正面が写って初めてマリウポリというのがわかる。そういった構成が映画としても実に巧みに組み立てられていたなと。この映画の素材に取り組んだスタッフたちが、監督の遺志をきっと物凄く大事にして、この映像を何とかして届けたいという気持ちを持ってやったんだなというのが、映画を観ながら感じました。
音楽が入っていないんですが、砲撃の音がずっと聞こえている。さっき言ったように、ここは本当に日常が破壊されてしまって、日常が残っていない土地なんだということをずっと音が訴え続けていたように思います。
身近な視点を描くことで生まれる、戦争に対して訴える力

──侵攻後に変わってしまったウクライナの街
ウクライナへの侵攻がはじまる直前ぐらいからツイッターなどでも注視していて、Googleマップで経路を入れると渋滞がわかる機能があるのですが、友人がおかしな渋滞があると言って、ロシア軍が国境の手前にいるように見えるというようなことを話したりしていました。また、Googleマップのストリートビューでみると、戦争が起こる前のウクライナの人々の生活がそこに封印されるように残っていて、普通に自転車でスーパーマーケットに買い物に行っている様子が写っている。キーウ郊外のブチャっていう街なんですけど、そこでは自転車に乗ったままロシア軍に撃たれて亡くなった人や集団墓地ができたり、そういった場所だったんです。最近までそこにあった以前の人々の姿を見ると、戦争が何を壊していったのかが本当によくわかります。
──マンタス監督は「戦争を撮りたいわけじゃない、人を撮りたいんだ」と言われていましたが、片渕監督と通ずるものは?
僕が第二次大戦中の映画を作ったのは、我々の中から戦争に対しての気持ちとか記憶とかが消えていくことに対して、もう少し繋ぎ留めたいという気持ちがあったのですが、彼の場合はその中に入っていくわけですよね。クリミア危機の時にもマリウポリを撮影していたりして、そういう中に入っていくことには、意志としてのすごく大きなものが必要だなと思って、そこで自分も同じですとはなかなか言えないです。とはいえ、誰の上に爆弾が落ちてきて、誰の上に砲弾が落ちてくるのか、そこにいるのがこの映画で出てきた猫を抱っこして離さなかった子供だったりするかもしれない。そういう事を思うと、突然そういうものが愛おしくなる。それが戦争に対しての自分の気持ちを作っていくようなところがある気がします。
ちょっと前にロシアの軍事戦略を研究している東京大学 先端科学技術研究センターの小泉悠さんと対談させて頂いたのですが、小泉さんがたまたま「この世界の片隅に」を観たときに、それまではロシア軍の核兵器がこれぐらいの量があって、どういう戦力で使われるのかと思っていたのだけど、市民の側から描いた映画を観てふと思ったのが、そういうものが落ちてくるのが “自分の妻や娘の上何だな” ということを痛感したというようなお話をされていて、上から見ると街は地図のように広がっていて誰が住んでいるか一人一人見えないんですけど、人のいる地上から見える人々の姿っていうのは、戦争というものに対して大きく訴える力を本来なら持っているはずだなと思うんですね。ただ、それを人を人とも思わないっていうことが実際の戦争を動かしているわけなので、ある意味それでも変えられない痛さみたいなのを感じざるを得ないです。

一番最後に出てくる家を破壊されて、30年以上働いてきて「俺の生活はどうなるんだ」とおしゃっていた方が、大事に飼っていたセキセイインコの死骸を拾うんですが、ポイって放り投げるシーンがあります。あれはそれまでの鳥を飼っていた気持ちが本当に損なわれて、めちゃめちゃにされちゃったんだなという逆の表れのような気がして、あの場面こそ、心がこういう中で荒んでいく、あるいは感情を抱かないようにしないと生きていけないっていうか、そういうものを表していたような気がします。
最後に片渕監督は、「こんな風に映画を撮った映画監督がいて、彼が撮った作品ももちろんですが、マンタス・クヴェダラヴィチウス自身のことも皆さんの心に刻んでください」と締めくくった。 「マリウポリ 7 日間の記録」は、キネマ旬報シアター(千葉・柏)で8/4(金)まで上映されるほか、その後も長野、名古屋、埼玉、鹿児島などでも上映が予定されている。
制作=キネマ旬報社

作品概要
2022年2月24日、ロシアのウクライナ侵攻によって、廃墟と化した東部ドンバス地方のマリウポリ。その戦禍の惨状で生きる人々の7日間を、私情や感傷を交えずに記録し、リアルに追体験させるドキュメンタリー。監督はリトアニア出身で、人類学者からドキュメンタリー監督に転身したマンタス・クヴェダラヴィチウス。2016年にマリウポリの人々の日々の営みを記録した「Mariupolis」(日本未公開)を発表した監督は3月に現地入りし、破壊を免れた教会に避難していた数十人の市民と生活を共にしながら撮影を開始した。カメラに収められたのは、死と隣り合わせの悲惨な状況下でも、普通におしゃべりを交わし、助け合い、祈り、料理をし、タバコを吹かし、また次の朝を待つ住民たちの姿だった。だが3月30日、監督は同地の親ロシア分離派に拘束され、殺害されてしまう。助監督だった監督のフィアンセによって撮影済みの素材は遺体とともに帰国し、製作チームが本作を完成させた。2022年5月、第75回カンヌ国際映画祭で特別上映され、ドキュメンタリー審査員特別賞受賞。
今後の上映予定
■千葉 キネマ旬報シアター 7/22(土)~ 8/4(金)
■長野 長野相生座・ロキシー 7/28(金)~ 8/3(木)
■名古屋 大須シネマ 8/5(土)~ 8/6(日)+ 8/16(水)~ 8/18(金)
■埼玉 深谷シネマ 8/6(日)~ 8/12(土)
■鹿児島 ガーデンズシネマ 8/7(月)+ 8/9(水)
■埼玉 川越スカラ座 8/12(土)~ 8/18(金)
監督:マンタス・クヴェダラヴィチウス
 リトアニア北部ビルジャイ出身。ヴィリニュス大学歴史学部を卒業。専攻は考古学。2001年から2003年にかけてはニューヨーク市立大学大学院センターの文化人類学博士課程に入学し、2007年にはオックスフォード大学を卒業して社会文化人類学の修士号を取得。2013年にはケンブリッジ大学から社会人類学の博士号を取得した。マルチリンガルであり、母国語のリトアニア語の他、英語、ロシア語、スペイン語、ギリシャ語を話す。人類学者から映画監督に転身したクヴェダラヴィチウスは、類まれなヒューマニズムと映像センスで紛争地帯の空気を伝えてきた。フィンランドとリトアニアの合作で、アキ・カウリスマキがプロデューサーを務めた『Barzakh』(2011年)でドキュメンタリー監督デビューを果たし、ベルリン映画祭ほか各賞を受賞した。2022年3月30日、ウクライナ、マウリポリで死去。
リトアニア北部ビルジャイ出身。ヴィリニュス大学歴史学部を卒業。専攻は考古学。2001年から2003年にかけてはニューヨーク市立大学大学院センターの文化人類学博士課程に入学し、2007年にはオックスフォード大学を卒業して社会文化人類学の修士号を取得。2013年にはケンブリッジ大学から社会人類学の博士号を取得した。マルチリンガルであり、母国語のリトアニア語の他、英語、ロシア語、スペイン語、ギリシャ語を話す。人類学者から映画監督に転身したクヴェダラヴィチウスは、類まれなヒューマニズムと映像センスで紛争地帯の空気を伝えてきた。フィンランドとリトアニアの合作で、アキ・カウリスマキがプロデューサーを務めた『Barzakh』(2011年)でドキュメンタリー監督デビューを果たし、ベルリン映画祭ほか各賞を受賞した。2022年3月30日、ウクライナ、マウリポリで死去。
©2022 EXTIMACY FILMS, STUDIO ULJANA KIM, EASY RIDERS FILMS, TWENTY TWENTY VISION
後援:リトアニア共和国大使館
配給:オデッサ・エンタテインメントTOMORROW Films.
配給協力:アーク・フィルムズ