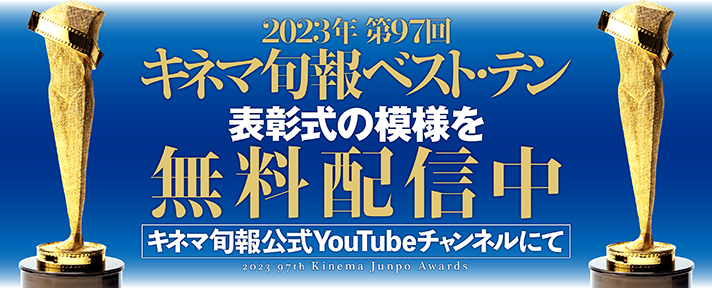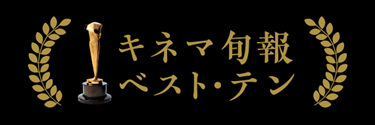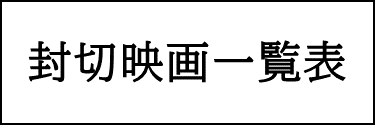5月の花嫁学校の映画専門家レビュー一覧
-
映画・音楽ジャーナリスト
宇野維正
邦題の「5月」は5月革命と呼応している。映画では主にヌーヴェル・ヴァーグの諸作品を通して、我々は革命側の視点、あるいは都市(=パリ)側の視点から知ってるつもりになってきたが、その時代のフランス社会では妻は夫の許可がないと自分名義の銀行口座を開くこともままならなかった、というような地方の強固な保守性が描かれている。それを肩肘張ったプロテストではなくライトコメディとして提示できるのは、そこから成熟を経てきた社会の証か。日本はまだ「革命」以前。
-
ライター
石村加奈
ジュリエット・ビノシュの魅力がふんだんに活かされたヒロインだ。夫を喜ばせるために、家に花を飾ろうと大真面目に唱える花嫁学校の、堅物校長然とした序盤から既に、ピンクのスーツからは個性が滲み出ていた。急逝した夫の借金を背負い、学校の再建に奔走する中、初恋の人との再会を経て、どんどん軽やかになっていく彼女。新しい自分へのギフトを、義妹(ヨランド・モロー)に披露してみせる夜の二人のやりとりは、女学生よりもみずみずしかった! パリに向かうラストも爽快。
-
映像ディレクター/映画監督
佐々木誠
68年のフランス、5月革命直前の家政学校が舞台、という女性の意識の変化をダイレクトに描いたコメディタッチの作品。50年以上前を描いているのに今の時代に観ることがピッタリで、それがいろんな意味でフェミニズムをめぐる問題の根深さを感じた。登場人物たちの設定が緻密に作り上げられているのでそのアンサンブルが楽しい。突如ミュージカル調になって、先進的な活動をしてきた著名な女性たちの名前を列挙して歌い上げるのはさすがにダイレクト過ぎるとは思ったが。
1 -
3件表示/全3件