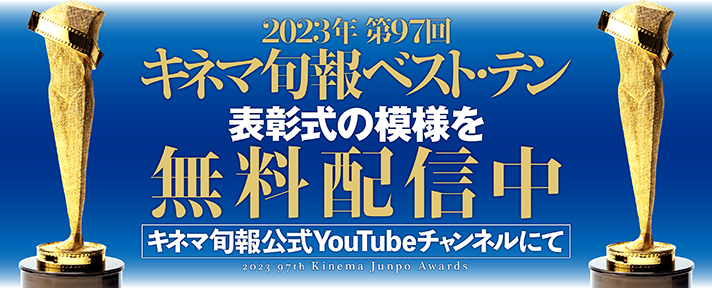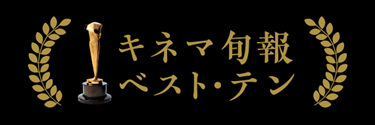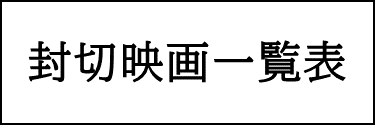「クレーヴの奥方(1961)」のストーリー
16世紀、アンリ2世(レイモン・ジェローム)下のフランスの宮廷。そこでは折しもクレーヴ公(ジャン・マレー)とシャルトル嬢(クレーヴ公夫人・マリナ・ヴラディ)の婚礼を祝う舞踏会が開かれていた。その席で宮廷きっての好男子ヌムール公(ジャン・フランンワ・ポロン)と偶然踊ることになったクレーヴ公夫人は、20歳も年上の夫には感じたこともないような胸の高まりを彼に抱き、一方のヌムール公もクレーヴ公夫人に強く惹かれてゆくのだった。そんな折、ジュー・ド・ポームの試合の際に公夫人の従兄シャルトル公が落とした愛人あての恋文を、皇太子妃メアリー・スチュアートを通じてクレーヴ公夫人に保留を任される。王妃カトリーヌ・ド・メディチ(レア・パドヴァーニ)の愛人であるシャルトル公は、王妃以外の愛人の存在が明るみに出るのを恐れ、ヌムール公に手紙を取り返してもらおうとした。彼の懇願に手紙を焼き捨てるクレーヴ公夫人だったが、王妃がその手紙を要求していると知り二人で手紙を書き直すが、愛の言葉を綴ってゆくうちに我がことのように感じるクレーヴ公夫人とヌムール公の愛は一層強くなってゆく。恋に動揺するクレーヴ公夫人は胸のうちを夫に打ちあけ、それを立ち聞きしたヌムール公は有頂天になる。その後、槍試合の折クレーヴ公は妻の恋愛相手に気づくことになるが、その試合の最中に折れた槍の破片が目の玉に入り、その傷がもとでそのまま崩御してしまう。ある夜、ヌムール公がクレーヴ公夫人の寝室に入ってゆくのを目撃した道化(ピエラル)が、そのことをクレーヴ公に注進する。二人の間にやましい事は何もなかったが、公は妻の不貞を早合点し心痛のあまり床につき、妻の弁明に耳も貸さずに息絶える。自責の念に駆られた公夫人は隠遁生活を送るようになり次第に衰弱していった。死が間近に迫った彼女は、ヌムール公への愛の手紙を書くが、それを手渡す暇もなく息を引きとるのだった。