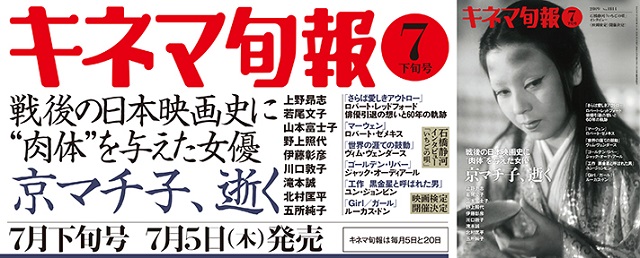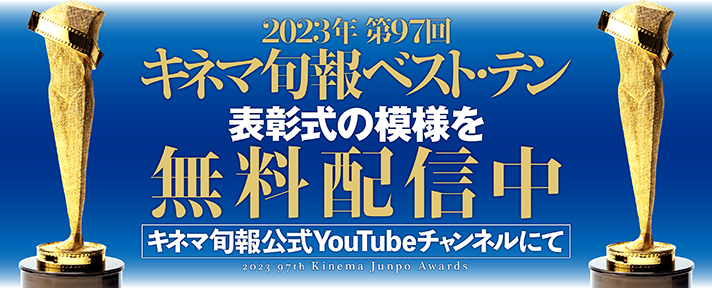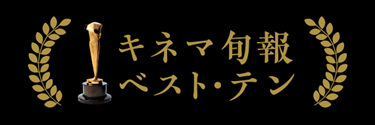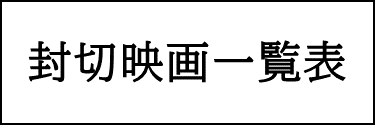あまりに痛く、美しいトランスジェンダーの少女がふみだす一歩 映画『Girl /ガール』
- Girl /ガール
- 2019年07月22日
ガールの、この先は峻厳にも薔薇色に染まる

(c)Menuet 2018
『ガール』という映画に予備知識もないまま興味をもったのは昨年5月、カンヌの映画祭公式ページで授賞セレモニーの中継を見た時のことだ。カメラ・ドールを受賞した監督ルーカス・ドンと共に登壇した金髪のひとりは、小公子のような黒いリボンで襟元を飾り、消え入りたげな微笑みを湛えてそこにいた。少年とも少女とも見える美しい人の、周囲の空気をしんと澄み返らせるような清冽なたたずまいに惹きつけられてそのまま受賞者たちの会見も見逃せない気持ちになっていた。会見の席でもまた監督の脇にどこまでも控えめにいた彼、ヴィクトール・ポルスターが質問に真摯な答えを返しつつ青白い頬から首筋まで、みるみる痛ましいほどに紅潮させる様がくっきりと目に焼きついた。
薔薇色に染まった肌が象る純真。その痛々しさとも映る記憶。それが、一年を経て見ることの叶った映画『Girl /ガール』のみつめるトランスジェンダーのヒロインの抱えた幾層もの痛みと向き合ううちにふるふると蘇ってきた。トウシューズを着け爪先立ちで踊る女性の踊り手としてバレエを究めること。心身共に女の子になること。そのどちらが欠けても真の自分になれないと思いつめて、文字通り血のにじむレッスンに励み、ホルモン療法、さらには性別適合手術をも希求するララを、水面下のあがきを見せない白鳥の清雅で体現し得るひとり、ポルスターと出会えた監督と映画の幸福を改めて嚙みしめた。

(c)Menuet 2018
実在のダンサーに触発されたドンの映画は、ララの16歳の誕生日に父が語る「いろいろ大変なことはあった」とのひとことで、性のアイデンティティをめぐる外界との闘いをかいつまみ、潔く脇に置く。それよりは、思う通りの自分となるためにララがかいくぐる彼女自身との闘いに焦点を合わせることを選ぶ。確かにララの新人生を祝福する誕生パーティで「3人目の男の子」を妊娠中と実母がきめる脳天気な発言(インタビューで監督も不在と述懐している母をこの場面に敢えて見出してみたいのは、その発言がララ/ヴィクトールをまだ「一人目の息子」と捉える彼女の無意識の罪を示唆すると見ても面白いかもと思えるからだ)のように、悪意なき人のむごさや鈍さ、世界の厳しさを垣間見せはするものの、映画はそれより理解を湛えた大人たちの中で、すべてをひとりで抱え込み「大丈夫」と日々の痛みを裡(うち)に裡にと沈殿させるヒロインの辛さこそを辛抱強くみつめようとする。
ドキュメンタリーのように演技を超えるポルスター

(c)Menuet 2018
シングルファーザーとして子供たちと暮らす父とララとの関係はとりわけ印象的だ。「君の名前で僕を呼んで」や「ビューティフル・ボーイ」の父とも通じる彼が注ぐ大きな愛。ゆっくりと思春期を愉しめ、あっという間に終わるから――と投げ掛けられる励ましの言葉。その100パーセントの善意ゆえに、もしかしたら紋切型の反抗も封じこめずにいられなくなるララの辛さがいっそう胸に迫る。そんな父やセラピストや医師の前で、ララは鎧のように微笑みの仮面を纏い続ける。そういえばと思い出すのは20世紀の初め、世界初の適合手術を受けた“デンマークの娘”リリー・エルベを描いた『リリーのすべて』のことだ。妻に後押しされて画家アイナー・ヴェイナーがトランスジェンダーの生を生き始めた自由と、身についた抑制の狭間で臆病な微笑みに閃光然とした瞬きをよぎらせる様。やがて手術によって身体的にも真の自分を全うする時、その瞬きがみごとに駆逐されていく様。演じたエディ・レッドメインはそんなひとりを英国俳優ならではの外側からのアプローチで完璧に形にしてみせていた。

かたやドンの映画はドキュメンタリー然とポルスターの演技を超えた佇まい、さらには肉体そのもののありさまを掬い上げていく。トウシューズを脱いではがされるテープ、血まみれのつま先の赤。レオタードの下の性器のふくらみを押さえつけるテープをはがすとその肌が鞭打たれたように赤く染まっている。そこで目を撃つ痛み。蛇口で水を含み、高窓に風を呼んで耐えるララを苛む肉体的な痛みが心のそれをも射抜き、ひりひりと見る目にも沁みてくる。そうやって日々繰り返される苦闘を記録する映画にやがて痛みの記憶を背負い込むように赤バックの場面がじわじわと増殖していくことも見逃せない。そうして開幕部分、諌める父をしり目に「もう遅い」と望み通り耳にピアスの穴をあけていたララが静かに選ぶデスパレートなその先の一歩――。
『無防備』(市井昌秀監督)と通じる「共感と衝撃」

(c)Menuet 2018
実は本稿をと送って下さった編集の川村さんのメールには市井昌秀監督の『無防備』を見た時の「共感と衝撃」と通じるとあって、最初はひとつもぴんとこなかったのだけれど、事故で子供を生めなくなった女(木下)と臨月の女、ふたりの関係を日々の暮しの中で丹念にみつめた挙句、走り出す映画の先に置かれた無修正の出産シーンを振返る時、目からうろこのような感覚がじわじわと襲いかかってきた。その時の原稿を少し長いが抜粋してみたい。「無論、新たな命の誕生を見届けることで殺意も憎悪も突破して自らも再び新しく生き始めた木下の笑顔のストップモーションに癒しや救いや赦しばかりを探るのはあまりに安易というものだろう。映画は終わり、そこで終わる筈もない世界に向けて観客はまた歩み出さずにはいられない。それでも、苛酷な世界に向けて小さな頭をはみださせた赤ん坊の無防備、その強さをまざまざと目撃した事実は残る。目撃させた映画が、むきだしの命の源を世界に向けて突きつけて露悪趣味とも感傷とも無縁の真空地帯、その峻厳をそこでもぎとっていた事実もまた観客の胸に美しく刻まれているだろう」
ララの薔薇色の痛みの先、選ばれた一歩も同じ峻厳をもぎとっていると思う。
文=川口敦子/制作:キネマ旬報社
『キネマ旬報』7月下旬号の詳細はこちらから↓