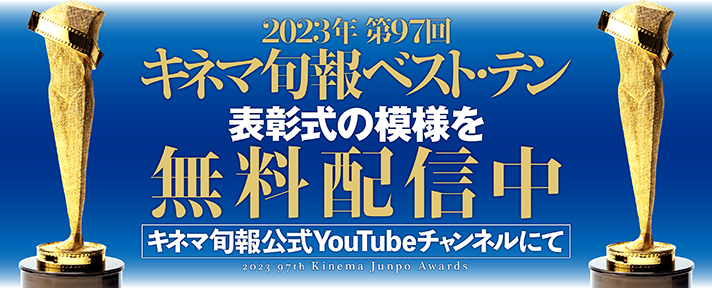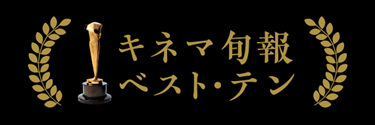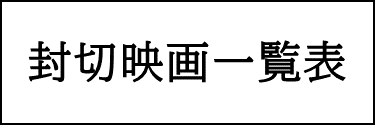記事
「とから始まるもの」の検索結果
(50件)
記事
「とから始まるもの」の検索結果
(50件)
-
柳楽優弥×黒島結菜×堤幸彦監督。衝撃コミック原作の獄中サスペンス「夏目アラタの結婚」
2024年4月19日連続バラバラ殺人の犯人である死刑囚、“品川ピエロ”こと品川真珠。彼女を訪ねた元ヤンキーの児童相談所職員・夏目アラタは、事件の真相を探るべく《獄中結婚》を申し出る──。『医龍-Team Medical Dragon-』で知られる乃木坂太郎の同名ベストセラーコミックを、柳楽優弥と黒島結菜の共演で堤幸彦監督により映画化した獄中サスペンス「夏目アラタの結婚」が、9月6日(金)より全国公開。ティザービジュアルと特報映像が到着した。 特報映像は声優・緒方恵美のナレーションで映画を紹介。ガタガタの歯並びで不敵に笑う真珠(黒島結菜)と、翻弄されていくアラタ(柳楽優弥)──両者の駆け引き、そして予期せぬ結末から目が離せない。 https://www.youtube.com/watch?v=hQltIF4x9eE 〈コメント〉 柳楽優弥 脚本を読ませていただき、夏目アラタというキャラクターは今まで自分が演じたことがない役柄だなと感じました。同時に、スリリングなストーリーを含めた作品そのものに魅力を感じ、是非にとオファーを受けさせていただきました。 現場では堤幸彦監督を筆頭に「いい作品にしたい」という高揚感を常に保ちながら、毎日撮影に集中することができました。アラタが対峙することになる真珠は、狂気と底知れない怖さをあわせ持つ連続殺人事件の容疑者であり死刑囚です。黒島さんが魅力的に、そしてとてもかっこよく演じられていたので、一緒にお芝居をするのがとても楽しかったです。 この作品は「もしかしたらありえるかもしれない…」という、ファンタジーとリアリティのギリギリのラインを攻めているところが個人的にはすごく面白いなと感じています。 アラタと真珠がどんな結末を迎えるのか。是非ご期待ください。 黒島結菜 私が演じた真珠は、表情がコロコロ変わり何を考えているかわからない、全く掴みどころのない役です。とても難しい役だったのですが、監督の堤さんやスタッフの皆さんが信頼できる方々だったで、のびのび演じることができました。毎日ヘトヘトになりましたが…笑 原作にある不気味さや怖さをしっかりと表現するために、特徴的な真珠の歯はマウスピースを作りました。何度も試作し、納得できるものができたと思います。ぜひ注目してみてください。 柳楽さんとの共演はとても久しぶりでした。拘置所でのアクリル板越しのシーンや法廷でのシーンが多く、リアルな距離感のお芝居は少なかったですが、目がとても印象的なので、対面したときに吸い込まれてしまわないよう必死でした。柳楽さんとはエネルギーレベルでお芝居ができたのかもしれないと今になって思います。たのしかったです! 一言では言い表せない映画になりました。ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです! 堤幸彦監督 原作はミステリアスでスリリング、先が読めないストーリー性にグイグイと魅かれたのですが、それ以上にアラタと真珠の厭世的だけど強烈に愛を求めている姿に痺れました。 映画化では原作に描かれている唯一無二なキャラクターをなんとか立体化したく俳優と頑張りました。 柳楽氏はすっかり大人になっているのですが、少年のギラリとした視線を保ち続けていて安心しました。 そして、アラタの巻き込まれながらも目覚めた心情、それへの葛藤や裏腹な切なさを演じ切るとい う難役をきっちりこなしてくれました。 黒島さんは一言「ヤバい」です!見たことない彼女です。 ぜひ見てください! 乃木坂太郎(原作) 柳楽優弥さん、黒島結菜さんの2人が危険な化学反応を起こしそうな匂いを濃厚に漂わせていますね。原作者として真珠の歯並びの再現に本気の映像化を感じました! 「夏目アラタの結婚」 原作:乃木坂太郎「夏目アラタの結婚」(小学館ビッグコミックスペリオール刊) 監督:堤幸彦 出演:柳楽優弥、黒島結菜 配給:ワーナー・ブラザース映画 ©乃木坂太郎/小学館 ©2024映画「夏目アラタの結婚」製作委員会 公式サイト:natsume-movie.jp -
傑作『デカローグ』を完全舞台化―2024年7月まで、刺激に満ちた演劇体験が続く!
2024年4月18日[caption id="attachment_37360" align="aligncenter" width="1024"] 『デカローグ1 ある運命に関する物語』(右から)ノゾエ征爾、石井 舜、高橋惠子 / 撮影:宮川舞子[/caption] ポーランド映画の名匠クシシュトフ・キェシロフスキ監督(1941-1996)の最高傑作の呼び声高い「デカローグ」(1989)を、このたび35年という歳月をへだてて日本の精鋭演劇人が集ってその舞台化に挑戦、4月13日から東京・新国立劇場で上演されている。一口に舞台化と言っても、映画ファンならすでにご存じのように、これは並大抵の試みではない。なにしろ「デカローグ」という作品は10話の物語が連作の形を取って、合計上映時間10時間近いオバケ作品なのである。それをまったくコンパクト化したり、エピソードを減らしたりせず、舞台用にフィットするようにアレンジを加えながらも、全10話をコンプリートさせようという途方もない演劇プロジェクトとなった。現在、新国立劇場で上演されているのは、デカローグ1『ある運命に関する物語』/デカローグ3『あるクリスマス・イヴに関する物語』/デカローグ2『ある選択に関する物語』/デカローグ4『ある父と娘に関する物語』の4話分である。残りの6話分も含め、同劇場では7月15日まで上演が続いていく。 そう聞くと、なにやら観客は長時間にわたって座席に縛り付けられ、とてつもない苦行を強いられるように想像してしまうが、意外なことに、むしろ通常以上に快適な演劇体験が待っている。1話あたりの上演時間は映像と同じように1時間前後の中編であり、1話分を終えると20分間の休憩が入る。その20分間で、いま見終えたばかりの物語の投げかけてきたものの意味や、もたらした感情の機微を、落ち着いて噛みしめ、吟味し、次のエピソードに臨むための準備もできる。筆者は今回の4話分を1日で完走したのだが、本当に充実した時間で、苦行とは無縁の演劇体験だった。 では、小川絵梨子と上村聡史の両演出家によって実現される今回の「デカローグ」舞台化の意義とはいかなるものだろうか。意義を考える前にまず前提となるのは、20世紀ポーランド演劇というものがヨーロッパ有数の前衛性で名高く、日本でも古くから多くの演劇人がその紹介に努めてきたという歴史的な背景である。ヴィトキェヴィチ、ゴンブローヴィチといった劇作家の戯曲が日本演劇人によって積極的に上演された上に、カントール、グロトフスキといった演出家の仕事や前衛的理論が多大なる影響力をもって受容されてきたのである。 [caption id="attachment_37361" align="aligncenter" width="1024"] 『デカローグ2 ある選択に関する物語』(右から)前田亜季、益岡 徹 / 撮影:宮川舞子[/caption] そして今回、まずは4話分を客席から見ながら改めて思い起こされたのが、キェシロフスキ映画というのはずいぶんと演劇との親和性が高いのだな、ということだった。キェシロフスキ作品は、これ見よがしのスケール感を誇ったりしないし、大文字の歴史で風呂敷を広げたりもしない。むしろ、等身大の人間たちのうごめきをじっと注視する。どこにでもいる、そして欠点だらけの人間という存在の喜怒哀楽、心配、愛憎、エゴイズム、執着、追憶、心的外傷、そしてなにかを示す徴候に寄り添っていく。「デカローグ(Dekalog)」とは、ポーランド語で旧約聖書における「モーセの十戒」のことである。神の御心に沿って人間に課せられた10の掟であるわけだが、この「デカローグ」全10話に登場する人々はいずれも十戒を立派に遵守できるような存在ではない。弱さゆえに、あるいは傲慢さ、不実さのために間違いを犯してしまう存在ばかりである。戦争、環境破壊、社会不安、経済システム不全、そして文明崩壊の危機が叫ばれる今日だからこそ、弱き人々の、過ちを犯してしまう人々の等身大の姿を見つめ、その存在に寄り添うような物語を語ろう、という企画者たちの遠大な意図が感じられる。 「デカローグ」の描く時代は、統一労働者党による一党独裁の末期となる1980年代、ポーランドの首都ワルシャワ。舞台は大型集合住宅である。このような画一的な大型の集合住宅建築はワルシャワの中心部から離れた郊外の国有地に多数造成された。舞台があっちこっちに移動したりせずに、集合住宅に暮らす人々の等身大の姿に目を凝らす。この点も「デカローグ」が舞台化に適している所以である。1箇所を舞台に複数の主人公たちの物語を並列的に語っていく話法を〈グランドホテル形式〉と呼ぶ。その名前の由来は、1932年にエドマンド・グールディングが監督したアメリカ映画「グランド・ホテル」(グレタ・ガルボ&ジョン・バリモア主演)だった。「デカローグ」はまさに〈グランドホテル形式〉のドラマである。 デカローグ1『ある運命に関する物語』ではクシシュトフ(ノゾエ征爾)と幼いパヴェウ(石井舜)の父子、クシシュトフの姉イレナ(高橋惠子)が厳しい運命に晒され、デカローグ3『あるクリスマス・イヴに関する物語』ではヤヌシュ(千葉哲也)とエヴァ(小島聖)が不倫愛を再燃させる。デカローグ2『ある選択に関する物語』では医長(益岡徹)の前に現れた人妻のドロタ(前田亜季)は闘病中の夫アンジェイ(坂本慶介)を尻目に、別の男性との間の子を妊娠している。デカローグ4『ある父と娘に関する物語』ではミハウ(近藤芳正)の残した「死後開封のこと」という手紙を一人娘のアンカ(夏子)が見つけてしまったことにより、隠蔽されてきた危険な真実がいっきに吹き出してしまう。 [caption id="attachment_37362" align="aligncenter" width="1024"] 『デカローグ3 あるクリスマス・イヴに関する物語』(右から)千葉哲也、小島 聖 / 撮影:宮川舞子[/caption] デカローグ1の主人公クシシュトフは、決定的な運命の結果がいままさに出ようとしている重大な局面で、フットワークの悪さを露呈する。サイレンが鳴りわたり、集合住宅の住人たちが慌てふためき、ヘリコプターのプロペラ音が頭上を通過しているというのに、クシシュトフは息子パヴェウの英語塾の先生に連絡を取ってみたり、近所の女の子に事情を尋ねたり、集合住宅の階段やエレベーターで昇降したり、トランシーバーで通信を試みたりと、大学教授としてのふだんの切れ者ぶりが肝心なときに影を潜めて、運命的な出来事が起きている現場になかなか辿りつかない。私たち観客はクシシュトフのフットワークの悪さに苛立ちを隠せないが、そのフットワークは私たちの自画像にほかならない。徴候はたしかにあった。しかしこれほど残酷なしっぺ返しを食らうほど、彼は罪びとなのか? その答えはどこからも返ってこない。この判定不在こそが十戒=デカローグの真の掟である。 ひとりとして完璧な人間なんておらず、誰もが欠点や罪を抱え、傷を負い、苦悩を内に宿しつつもなんとか生活している。その等身大の姿が、集合住宅の内部を覗き込むようにして開陳されていく。2でメインキャラクターだった医長は4では脇役にまわり、1で主人公だったクシシュトフは3では一歩行者として界隈にまぎれていく。登場人物のさりげない進退が〈グランドホテル形式〉の豊かなゲーム性を醸しつつも、例外的に1名だけ各話に登場する男がいる。亀田佳明が演じるこの男は、ときに湖畔で焚き火する男だったり、ときに病院の当直医だったり、必ず各話で容姿を変えながら登場し、一言もセリフを喋らずに、主人公たちの運命に干渉しないまま観察している。天使にも見えるし、作者の分身のようにも見える。 [caption id="attachment_37363" align="aligncenter" width="1024"] 『デカローグ4 ある父と娘に関する物語』(右から)近藤芳正、夏子 / 撮影:宮川舞子[/caption] しかしながら、今回の4話分の上演を見終えたいま、筆者にはこの「デカローグ」舞台上演版の真の主人公は、集合住宅そのものだという気がしている。キェシロフスキの映画版(本国ではポーランド公共放送「PTV」のテレビドラマとして発表された)では的確なモンタージュとロケーションによってリアリズム描写が徹底され、集合住宅の大型アパートメントは、社会主義末期の庶民の暮らしを〈グランドホテル形式〉で象徴的に提示するロケーションでしかなかった。ところが今回の新国立劇場のステージでは、アパートメントの構造がコーナーキューブ状に組まれて、空間そのものが骨組み化され、抽象性と可塑性が強調されている。キューブの中身はスプレッドシートのセルを書き換えるかのごとく、エピソードごとに自在に装飾替えがほどこされ、かえってその自在さが、現代生活の可逆性、没個性性、不安定性を炙り出している。ヨーロッパの演劇シーンでも高い評価を得てきた舞台美術家・針生康(はりう・しずか)によるセット構造そのものが、本作の真の主人公ではないか。演者たちはこのコーナーキューブ状の美術セットを上下左右に動き回るが、動き回れば回るほど、人間存在の卑小さを痛感させるしくみになっている。事の本質を醒めた眼で透過した、じつにおそるべき美術セットである。 一映画評論家としてのちょっとした推理であるが、針生康によるこのコーナーキューブ状の美術セットは、川島雄三監督の映画「しとやかな獣」(1962)における上下左右に積み木されたような団地セットにインスパイアーされたものではないか。高度経済成長期の東京・晴海団地をモデルに、大映の名美術監督・柴田篤二によって造形されたあのみごとなキューブ状の美術セットが、2024年の演劇プロジェクトで時ならぬ復活ぶりを見せたのかもしれない。そんなことを勝手気ままに考えながら帰途に着くと、なにやら1962年〜1989年〜2024年という時間が遥かなる飛翔を披露してくれたように思われ、心がふわっと軽くなった。 この〈グランドホテル形式〉の連作を全10話にわたり完走したとき、私たち鑑賞者の前にはいかなる光景が広がっているのだろうか。今年7月まで、刺激に満ちた演劇体験が続いていく。 文=荻野 洋一 制作=キネマ旬報社 「デカローグ」 デカローグ1~4[プログラムA、B交互上演]=2024年4月13日[土]~5月6日[月・休] デカローグ5・6[プログラムC]=2024年5月18日[土]~6月2日[日] デカローグ7~10[プログラムD、E交互上演]=2024年6月22日[土]~7月15日[月・祝] 会場:[東京]新国立劇場 小劇場 ▶公式サイトはコチラから -
巨大竜巻に前代未聞の作戦で対抗!「ツイスターズ」特報映像とビジュアル公開
2024年4月18日巨大竜巻が多数発生。寄せ集めチームが、前代未聞の大作戦で立ち向かう──。「ジュラシック・ワールド」の製作陣が贈るアクション・アドベンチャー「ツイスターズ」が、8月1日(木)より全国公開。ティザービジュアルと特報映像が到着した。 「ミナリ」のリー・アイザック・チョンが監督し、「ザリガニの鳴くところ」のデイジー・エドガー=ジョーンズ、「トップガン マーヴェリック」のグレン・パウエル、「トランスフォーマー/ビースト覚醒」のアンソニー・ラモスが出演。圧巻のVFXと熱いドラマを楽しみたい。 https://www.youtube.com/watch?v=jK73iSaEPSM Story ニューヨークで自然災害の予測・防止の仕事に熱中するケイト(デイジー・エドガー=ジョーンズ)。故郷のオクラホマで巨大竜巻が連続発生したと知った彼女は、学生時代の友人ハビ(アンソニー・ラモス)、竜巻インフルエンサーのタイラー(グレン・パウエル)と共に、竜巻内部に秘密兵器を仕掛けて撃退する一大計画に挑むが……。 「ツイスターズ」 監督:リー・アイザック・チョン 脚本:マーク・L・スミス 製作:フランク・マーシャル、パトリック・クローリー 出演:グレン・パウエル、デイジー・エドガー=ジョーンズ、アンソニー・ラモス、ブライドン・ペレア、キーナン・シプカ、デヴィッド・コレンスウェット 配給:ワーナー・ブラザース映画 © 2024 UNIVERSAL STUDIOS,WARNER BROS.ENT.& AMBLIN ENTERTAINMENT,INC. 公式サイト:twisters-movie.jp -
巨匠マルコ・ベロッキオが、ユダヤ人少年エドガルド・モルターラを教会が連れ去ったという衝撃の実話を映画化。2023年のカンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品され、ナストロ・ダルジェント賞で作品賞をはじめ7部門を受賞した「エドガルド・モルターラ ある少年の数奇な運命」が、4月26日(金)よりYEBISU GARDEN CINEMA、新宿シネマカリテ、ヒューマントラストシネマ有楽町、T・ジョイPRINCE品川ほかで全国公開される。青年期のエドガルドを演じたレオナルド・マルテーゼのメッセージ映像、著名人のコメントが到着した。 https://www.youtube.com/watch?v=WAzLyB3QOz4 〈コメント〉 幼少期に家族のもとから連れ去られ、信仰や人格を変容させられたエドガルド。取り戻そうとする家族と青年になったエドガルドとの確執は、植え付けられた信仰を巡る宗教カルトからの脱会トラブルを想起させる。幸せな家族を引き裂いたものの正体を描いた問題作。 ──鈴木エイト(ジャーナリスト・作家) 洗礼という儀式にすぎない行為が幼い子供とその家族の人生を歪ませていく物語。 観る人によっては混乱や怒りを覚えるかもしれません。 さらに残酷なのはその子供が宗教上の駒にされていく様です。 考え方次第で狂気が正義となってしまう現実を思い知らされる作品です。 ──惣領冬実(漫画家) 「あなたは神父となり、ローマ教会に人生を捧げるのだ」。時は 1858年。教皇法は「絶対もの」。ヘブライ人、7歳のエドガルド君に対しても。紡がれるのは宗教と世俗的な権力に汚された親の絶念、子供の無垢さ、親子思いの不撓不屈の物語だ。神の掟は母の涙の目前でさえ屈しないものなのか?魅惑的だが、残酷なイタリアを舞台にした夢中にさせる拉致事件。最後のフレームまで胸を膨らませる。 ──パントーフランチェスコ(慶應義塾大学病院精神神経科教室、精神科医) ユダヤ教徒だったナザレのイエスは、ユダヤ教を内部改革しようとしてユダヤ教守旧派の企みで処刑された。その後にイエスの弟子たちが広めたキリスト教は西欧社会の精神的インフラとなり、イエスを殺害したユダヤ人への差別や迫害はさらに激しくなった。この前提を知らないと現在の宗教地図が理解できなくなる。世俗と聖性、心の支えだけど危険。本作では信仰の二面性がこれでもかとばかりに描かれる。際どいテーマだ。正面から挑んだマルコ・ベロッキオの胆力には驚嘆する。 ──森達也(映画監督) ベロッキオはつねに社会に対し異議を唱えてきた監督である。子供が監禁され、母親が狂気へ向かう。いたるところに暴力がある。この世界は病気であり、歴史とは母親の悲しみなのだ。だが母親と違う神を信じるにいたった息子の悲しみを、誰が知ることだろう。 ──四方田犬彦(映画誌・比較文学) ある家族が強引に離ればなれにされ、永遠に引き裂かれてしまう悲劇の物語を丁寧に描きながら、同時に教会権力の衰退とイタリアという国の誕生につながる壮大な歴史をも見せてくる。このミクロとマクロを同時に描く離れ業こそ、ベロッキオ監督作品の醍醐味だ。 ──壺屋めり(イタリア美術史研究者) 約150年前の誘拐事件を描く本作は現代にも通じる多くの課題を突きつけている。信仰をめぐる戦争とカルト教団による洗脳は現在も続いているからだ。それに加えて、子どもの人格形成や親子のつながりとは何かという重い問いは見る者を揺さぶるに違いない。 ──信田さよ子(原宿カウンセリングセンター顧問・公認心理師) Story 1858年、ボローニャのユダヤ人街で、教皇が派遣した兵士たちがモルターラ家に押し入る。何者かに洗礼を授かったとされる7歳の息子エドガルドをキリスト教徒として養育するため、連れ去りに来たのだ。取り乱したモルターラ夫妻は、息子を取り戻そうとあらゆる手を尽くす。そして世論と国際的なユダヤ人社会に支えられ、その闘いは政治的な局面へ突入。しかし教会とローマ教皇は揺らいだ権力を強化するため、エドガルドの返還に応じようとしなかった……。 © IBC MOVIE / KAVAC FILM / AD VITAM PRODUCTION / MATCH FACTORY PRODUCTIONS (2023) 配給:ファインフィルムズ ▶︎ マルコ・ベロッキオが衝撃の誘拐事件を映画化「エドガルド・モルターラ ある少年の数奇な運命」
-
「ブルー きみは大丈夫」かわいい“空想の友達”が大集合した本ポスター公開
2024年4月18日子どもの時に一緒に遊んだ“空想の友達”が、もしも大人になった今でも、そばで見守っているとしたら──。「クワイエット・プレイス」のジョン・クラシンスキーが監督を務め、孤独な少女ビーが子どもにしか見えないモフモフな“空想の友達”ブルーと織り成す物語を描いた「ブルー きみは大丈夫」が、6月14日(金)より公開。本ポスターが到着した。 ブルーに体を預けるビー(ケイリー・フレミング)と隣人(ライアン・レイノルズ)。その周りを、ダンスが得意なブロッサム、探偵のコズモ、ピンク色をしたワニのアリー、おじいちゃんテディベアのルイス、ユニコーンのユニといった“空想の友達”が囲む。 子どもたちの豊かな想像力から生まれた“空想の友達”は、その子たちが大人になって忘れ去られた時、消えてしまう運命にある。ブルーも例外ではなく、新たなパートナーとなる子を見つけて彼を救うため、ビーは隣人の助けを借りて奮闘するが……。 クラシンスキー監督とレイノルズが「ピクサー作品の実写版のような映画を目指した」と語る、夢と感動の物語に期待したい。 https://www.youtube.com/watch?v=xbumLcgY3y0&t=2s ©2024 Paramount Pictures. All Rights Reserved. 配給:東和ピクチャーズ ▶︎ モフモフな“空想の友達”を救うため少女が大冒険。「ブルー AND THE SECRET FRIENDS」(仮題)