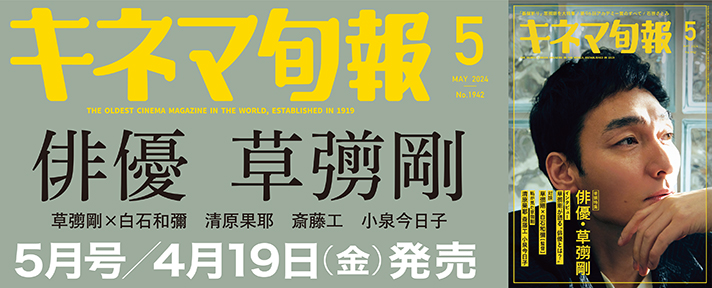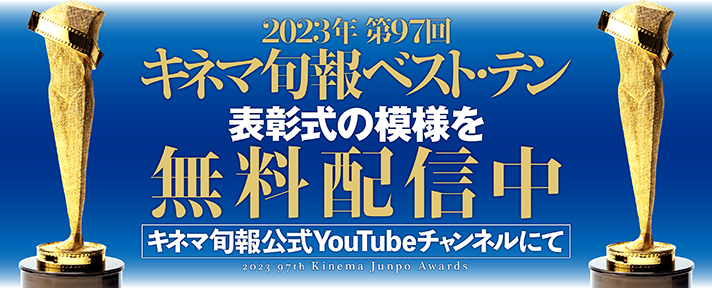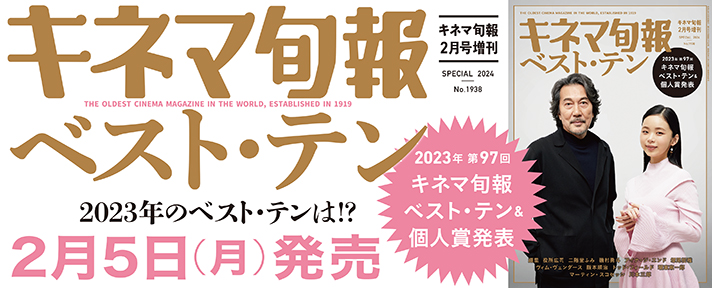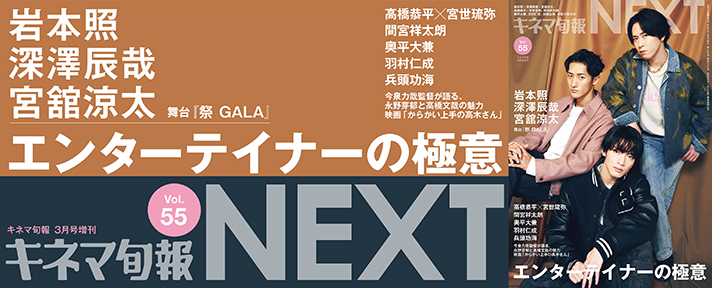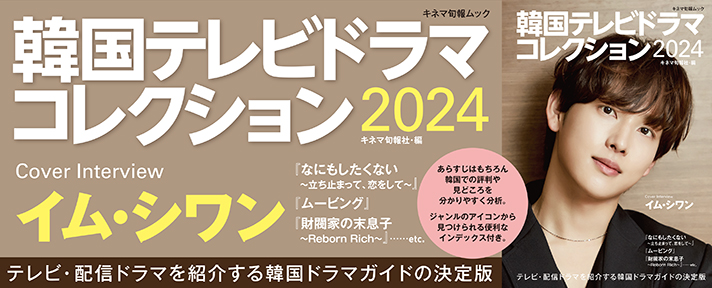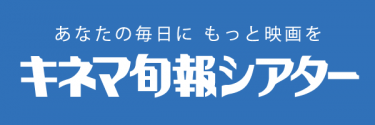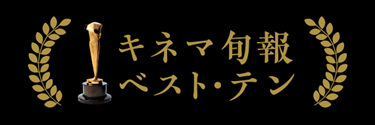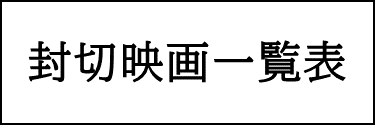- キネマ旬報WEB トップ
- 京マチ子
京マチ子の関連作品 / Related Work
作品情報を見る
-
地獄門 デジタル復元版
制作年: 1953第7回カンヌ国際映画祭グランプリ、第27回アカデミー賞最優秀外国語映画賞、衣装デザイン賞を受賞した大映の第一回天然色映画「地獄門」のデジタル復元版。撮影助手として本作に関わった森田富士郎氏の監修の元、オリジナル・ネガより三色分解したマスター・ポジなどを素材に当時の色彩を復元している。東京国立近代美術館・フィルムセンターと角川映画の共同事業。2011年5月2日NHK・BSプレミアムで放映。2012年4月28日、東京・京橋フィルムセンターにて特別上映。 -
羅生門 デジタル完全版
制作年: 19501951年ヴェネチア国際映画祭グランプリ金獅子賞、52年米アカデミー賞名誉賞(最優秀外国語映画賞)を受賞した黒沢明監督作品「羅生門」を、ハリウッド最高のデジタル技術を駆使し、映像・録音を本来の状態に蘇らせた。撮影は「雨月物語」の宮川一夫。出演は、「七人の侍」の三船敏郎、「地獄門」の京マチ子。100点 -
男はつらいよ 寅次郎純情詩集
制作年: 1976“男はつらいよ”シリーズ第十八作目で、おなじみのフーテンの寅が捲き起こす人情喜劇。今回は、学校の若い先生とその母を相手に、物語がくりひろげられる。脚本は「男はつらいよ 寅次郎夕焼け小焼け」の朝間義隆と山田洋次の共同、監督は「男はつらいよ 寅次郎夕焼け小焼け」の山田洋次、撮影もやはり同作の高羽哲夫がそれぞれ担当。90点