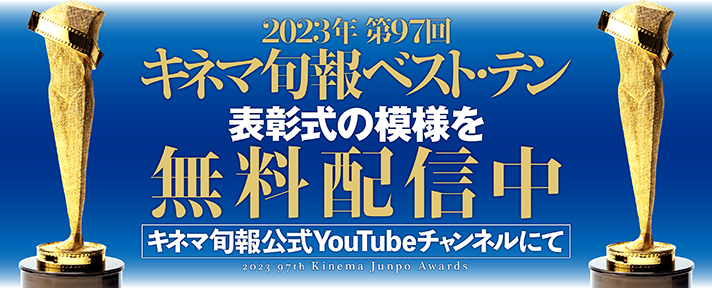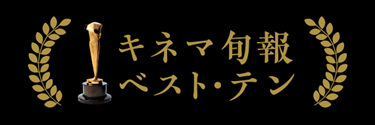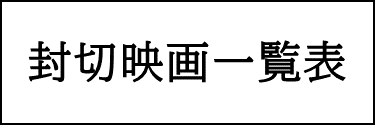ニュースNEWS
特集・評論ARTICLE
新作情報NEW RELEASE INFORMATION
週末映画ランキングMOVIE RANKING
名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)
公開: 2024年4月12日 公開 2週目変な家
公開: 2024年3月15日 公開 6週目オッペンハイマー
公開: 2024年3月29日 公開 4週目劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦
公開: 2024年2月16日 公開 10週目映画ドラえもん のび太の地球交響楽
公開: 2024年3月1日 公開 8週目機動戦士ガンダム SEED FREEDOM
公開: 2024年1月26日 公開 13週目四月になれば彼女は
公開: 2024年3月22日 公開 5週目ゴジラ-1.0
公開: 2023年11月3日 公開 25週目ゴーストバスターズ フローズン・サマー
公開: 2024年3月29日 公開 4週目オーメン ザ・ファースト
公開: 2024年4月5日 公開 3週目専門家レビューREVIEW
青春18×2 君へと続く道
公開: 2024年5月3日-
ライター、編集 岡本敦史
おお、チョン・モンホン作品のスターたちが長野県松本ロケで共演している、という感慨はあった。しかし、本格的な日台合作の青春映画という試みの面白さに、作品自体は届いていない。こういうベタな青春ドラマをただ新味なく撮っても、タイのGDHなどには全然敵わないし、今の観客に届けるための戦略を感じさせてほしい。特に回想パート。甘酸っぱさと気恥ずかしさは同義ではない。ただ、乗り鉄的には見どころが多く、クライマックスの舞台は大いに納得。そりゃ絵になるもの、只見線。
-
映画評論家 北川れい子
そういえば劇中、岩井俊二監督の映画が好きだ、という台詞があるが、台湾と日本を舞台にしたこのラブストーリーの人物や行動、エピソードも多分に岩井俊二的で、「新聞記者」「最後まで行く」の藤井道人監督・脚本にしては、これまでになく軽やか。ひょんなことから台湾のカラオケ店に住み込みで働きだした日本娘アミと、アミに恋した18歳の僕。18年後、人生の岐路にたった僕はアミに会うため日本へ。台湾と日本のどちらにも配慮した脚本は、みんないい人ばかりだが。
-
映画評論家 吉田伊知郎
清原果耶のベストアクトというべき魅力が引き出されており、その一点押しで評価したいが、ここは点を辛く。岩井俊二の「Love Letter」が劇中へ引用されており、物語もその影響下にあるが、それなら引用元を上回る要素がひとつでも必要なのではないか。日本各地で良い人と出会い、短時間で別れを繰り返すだけなので「幸福の黄色いハンカチ」の健さんみたいな行くに行けない焦燥がない。福島が大きな位置を占め、過去と向き合う物語なのに、震災や原発も透明化されている。
正義の行方(2024)
公開: 2024年4月27日-
文筆家 和泉萌香
サスペンスドラマが始まるぞ、というくらいにスタイリッシュなオープニングだが、これから語られ問われてゆくのは女の子ふたりが殺され、犯人とされた男性が、最高裁で確定してから二年あまりで死刑になった実際の事件のこと。監督が聞き出す事件の当事者たちの言葉の数々はすさまじく、日本の死刑制度と、現在進行形でおこっている暗澹とした現実にも思いを伸ばすとともに、生身の人間の顔を映し刻みつけることの重さと<パワー>を持っているのが映画であると改めて震えた。
-
フランス文学者 谷昌親
犯人とされた男にはすでに異例の早さで死刑が執行され、真相は永遠にわかりようがないが、粘り強く丹念な取材によって殺人事件の輪郭をみごとに浮き彫りにしていて、ルポルタージュとして観るなら、圧倒的なすばらしさだ。それぞれの立場からの証言や主張が交錯するさまはスリリングであると同時に、人間が抱える闇や社会のひずみをあぶりだしている。しかし、映画作品として観る場合、関係者たちのひとりひとりが過ごした事件からの30年あまりの時間の手ざわりがほしいように思う。
-
映画評論家 吉田広明
死刑が執行されるまでの経緯、再審請求する弁護士、捜査の問題点や自身の報道姿勢について検証する新聞の三段構え、重厚な作りで見ごたえがある。弁護士や新聞の検証で、警察の見込み捜査、状況証拠の弱さなどの疑義が明らかになってくる。問題なのはそれに乗っかった新聞の報道であり、間違いを認めようとしない司法なのだが、新聞は自己検証した、では司法は?というのが本作最大の問いだ。日本の正義の女神像は目かくしをせず、右顧左眄して判決を下すという言葉が核心を突く。
システム・クラッシャー
公開: 2024年4月27日-
映画監督 清原惟
児童養護施設を転々としている、問題を抱える子を丁寧に取材して制作したという経緯がひしひしと伝わってくる。なにより、主人公の女の子を演じた俳優の演技と演出が力強い。破滅的になりたいわけではないのに、そうなってしまうこと。とんでもなく破天荒で衝動的で暴力性の高い子の役を、こんなにもリアリティを持って演じられることもすごいし、彼女の弱さや、周りと同じようにできないが故の魅力も表現されていた。衣裳として主人公が着ている服の鮮やかさがいつまでも目に残る。
-
編集者、映画批評家 高崎俊夫
不敵な面構えの9歳の少女にとって世界とは“根源的な違和”の集積にすぎないのだろうか。幼少期に父親から受けたトラウマというとりあえずのアリバイをもかなぐり捨て、理不尽なる怒りに突き動かされ、彼女はあらゆる支援施設からの遁走を試みる。自然に抱かれた隔離療法のトレーナーとの束の間の牧歌的な時間さえ、自らぶち壊してしまう異様なまでの破壊への意志はどこから生じたのか。かつてトリュフォーや浦山桐郎が切実な想いを込めて描いた“不良少年”“非行少女”の残像すらここにはない。
-
映画批評・編集 渡部幻
金髪にピンクの服。愛嬌もあるが、瞳の奥に猛烈な怒りと無理解への憎悪が滲んでる。9歳の少女役のヘレナ・ツェンゲルの演技力が驚異的で、母親の愛を求める少女の暴発は凄まじい。受け入れ先の施設もなくなってきていて、暴れるたびに母親との生活から遠ざかる。だから少女は逃げる。疾走の映像が美しい。しかし一体どこへ? やはり9歳の少年を描いた「かいじゅうたちのいるところ」を思い出させたが、このドイツ人女性監督が少女に寄せた共感、パンキッシュなエネルギーと解放感は他に比すものがない。
エドガルド・モルターラ ある少年の数奇な運命
公開: 2024年4月26日-
文筆業 奈々村久生
持って生まれたものよりも育つ環境が人を作る。その可能性と残酷さ。社会や政治の時勢に利用される宗教の力と脆さ。ベロッキオには無駄がない。必要最低限のカット。無駄がなさすぎて、映画が終わった瞬間に潔くシャッターを降ろされるような問答無用感がある。ユダヤ教とキリスト教の関係やローマ教皇の影響下における信仰については、その背景のもとに育っていなければおそらく完全には理解し得ないが、これがたとえ新興宗教だとしても原理は同じであることが事の重さを突きつける。
-
アダルトビデオ監督 二村ヒトシ
人間にとっていちばん大事なのは心の自由だと思うのだが、しかし心が自由であることなんて人間に可能なのかとも思う。なにかに洗脳されていなかったら人は人間になれないのではないか。暴力で連れ去られ、親が信じているのとは別の、こう生きたほうが幸せになれるという生きかたを教えこまれる。そういう宗教と宗教の戦い、倫理と別の倫理の争いに巻き込まれることを人間はずっとやってきたのか。この映画で語られているとても大きな歴史の問題は、僕にはどう捉えていいのかわからない。
-
映画評論家 真魚八重子
エドガルドは母との別れで泣くような感情も見せるが、基本的には言われるがまま動く人間だ。ユダヤ人でありつつ、派手な教皇に対しスターへの憧れの眼差しを向ける。二つの生きる道の岐路に立つ彼が、同時に引率者を亡くすと空っぽになり、この数奇な運命は彼には重すぎてむごい。壁がアップになるとき、それは必ず向こう側から打ち壊されるためだという、映画のお約束にスカッとする。またエドガルドが磔刑に処されたキリスト像のくさびを抜くシーンも、心が射られた思いがした。
悪は存在しない
公開: 2024年4月26日-
文筆家 和泉萌香
空の道から地の道へ、映画は道を途切れさせ、男は斧を振りかざし薪を割り、車は無邪気に遊ぶ子供たちへと接近し、音楽はぶち切られ、切断から切断へ……。不穏さを際立たせる音の数々と、真っ白な雪の厳かな美しさ、やや露骨に感じられるくらいのカメラワークが織りなす濃密さは、やっぱり外から遮断された映画館で見なくては。印象は真逆ながら、同じタイミングで鑑賞した「辰巳」で発せられるセリフ──男の性=セックスと暴力、殺しに関する──が思わず響いた。
-
フランス文学者 谷昌親
「ハッピーアワー」で組んだスタッフやキャストが複数参加しているだけに、「ドライブ・マイ・カー」以上に濱口竜介監督らしい作品と言えるかもしれない。主人公の巧を演じる大美賀均はもともとスタッフで、台詞まわしもぎこちなく感じられるが、終わってみれば、まさに巧という人物以外のなにものでもない。森のなかを人が歩き、水を汲み、薪を割る、ただそれだけで画面が活気づく。鳥のさえずり、風やせせらぎの音、それらにかぶさるように流れてくる石橋英子の音楽も印象的だ。
-
映画評論家 吉田広明
山間地にリゾート建設を図る企業、形だけの説明会でお茶を濁すはずが、担当者が地元住人に感化される。神宮再開発を連想させる問題提起にも、「偶然と想像」につながるコメディにも見える作品。車の中での長い会話が事態を転回させる点も監督らしい。冒頭の長い移動など、音楽家のライブ用映像の名残だろうが、映画としてあれは要るのかなど疑問は残る。みんな悪い人間ではないという意味で「悪は存在しない」が、地元民に「悪意」がないわけではないというズレが露わになる衝撃。
青春(2023)
公開: 2024年4月20日-
映画監督 清原惟
中国の個人経営の縫製工場に勤める人々のドキュメンタリー。住居と職場が同じ集合住宅内にあるということもあって、仕事と生活が渾然一体となっている。皆とても仲がよさそうで、まるで家族のように暮らし仕事をしている。部屋もほとんどが相部屋で、働いている時間以外も一緒に食事をしたり音楽を聴いたりして、仕事の賃上げの交渉も一丸となってやっている様子に、人々のコミュニティのあり方について考えされられたし、自分もその中に暮らしているかのように時間を過ごした。
-
編集者、映画批評家 高崎俊夫
ワン・ビンが描く長江のデルタ地域にある小さな町の衣料品工場で働く農村出身の若者たちの初々しい青春群像を見ていると、“変われば変わるほど同じだ”と呟きたくなる。日本の不動産を買い漁る富裕層の対極にある彼らこそが中国経済を深層で下支えしているのだ。さらに中国の都市部との途方もない格差構造がじわりと滲み出す。同じ20代の経営者との賃上げをめぐる攻防。いくつものカップルたちが織りなすたわいない戯れ言や親密な触れ合い、寄る辺なさまでが怜悧な視点で切り取られている。
-
映画批評・編集 渡部幻
ワン・ビンは中国経済の一翼を担う長江デルタ地域の出稼ぎ労働者たちの特異な環境を捉え、文字では到底伝わらないだろう生活臭を充満させる。灰色の衣料品工場にミシン。灰色の空、灰色の生活、室内も室外もゴミだらけだ。カメラは若者たちを追う。みんなタバコを吸い、カップ麺を食べる。会話の中心は恋、妊娠、結婚、そして賃上げの交渉。肉体的な距離が密接で、やたらにじゃれ合う。ぼくに身近な20世紀後半の日本を思い出したが、彼らの手にはスマホが握られている。これもまた“21世紀の青春”なのだ。
辰巳
公開: 2024年4月20日-
文筆家 和泉萌香
歯車の部品が転がった、車のはらわたもはみ出る整備工場で、文字通り彼彼女らの体液も飛び散り絡み合い、肌のきめもすべて太陽にあぶり出され、暴力から発せられる汚い言葉が飛び交う。感傷や愛情にからめとられることなく、?き出し(になりすぎるくらい)のエネルギーをみなぎらせたまま、そのエネルギーのままに動き続け、穏やかではないカメラもここは、と揺るぎなくとらえるふたりの顔。血みどろのはて、海や草むらと同様にさらされる、人間の肌が湛える確かな美しさを喚起する。力作。
-
フランス文学者 谷昌親
日本映画には珍しいハードなノワール物だ。水辺の街の無機質さが人物たちの非情な生き方に重なり、陰影のある独特の虚構世界が作り上げられている。物語としては、「レオン」の日本版といった感じだが、少女の年齢が高いこともあり、ただ守ってもらうだけの存在でないあたりもおもしろい。自主制作でジャンル物を手がけ、しかもこの完成度になるということに驚かされるが、すぐれたジャンル映画を参考にしつつ、自分の求める世界を妥協せずに追求できたということなのかもしれない。
-
映画評論家 吉田広明
やくざの上前をはねた金を巡り、巻き込まれて死んだ姉の仇を撃とうとする妹に、同じやくざの一員で死んだ姉の元彼であった男が協力するという構図。主人公の男は自分が主体的に動くというより、受動的に引きずられるわけだが、その理由はあくまで情動であるという点に本作をノワールとする根拠はあるだろう。姉の断末魔の長い場面の痛ましさ、殺しが快感になるという職業犯罪者に対し、殺す度に吐く妹の姿が、死の重さを感じさせるだけに、主人公の情動は説得的になっている。
マンティコア 怪物
公開: 2024年4月19日-
文筆業 奈々村久生
群青いろの新作「雨降って、ジ・エンド。」との相似が妙に腑に落ちる。カルロス・ベルムト監督ならではのトリッキーな作劇と抑制された語り口が効いていて、リアリズムではセンシティブになりすぎそうなところを絶妙なバランスで「表現」にスライドさせている。フィクションの矜持がうかがえるようなラストも見事。同じビターズ・エンド配給で昨年公開された「正欲」もテーマ的には同系譜に属しており、この題材は繰り返し描かれることによって、今後タブーから議論の対象になっていくと思う。
-
アダルトビデオ監督 二村ヒトシ
オタク男の妄想のモンスターがAIの暴走で実体化して悪さするホラーかと思ったら、そんな昔よくあった差別的な話じゃなくて、もっと地味な、つらい恋愛譚だった。異常な(って言いかたを僕はしたくないのだが)欲望をもってしまった者はどうやって幸せになればいいのか。日本の「怪物」は結果的にポリコレの人も反ポリコレの人もそれぞれが考えねばならないことを考えざるをえない映画になったわけだが、こっちの怪物にはできれば一生考えたくなかったことまで深く考えさせられてしまった。
-
映画評論家 真魚八重子
本作は主人公のとある秘密を隠して物語が進む。その核心に触れないように、話はずっと本題を避けた無駄話が続く。意図はわかるが、そのギミックに付き合わされる観客はたまったものではない。ある種の性的嗜好を持つ人々は、一生その欲望を経験できずに、妄想のままで終わらせなければならない。欲望を行動に移せば犯罪となり、その対象者に大きなトラウマを与えてしまう。それは確かに哀れであるが、もう一人の重要人物もいびつな共依存の欲望の持ち主で、ラストまで気持ち悪い。
異人たち
公開: 2024年4月19日-
文筆業 奈々村久生
主人公の内面世界と現実世界が渾然とした世界観。限られた登場人物と視点がその描写を可能にする。他者との関わりの少なさは自己の肥大を許し、それを妄想と呼ぶのは簡単だが、敢えてネタバレ前提で言うと(以下閲覧注意)「シックス・センス」のシステムをあくまでもドラマとして描いたのが大林宣彦版ともシャマランとも異なるところで、原作のエッセンスに近いかもしれない。愛の儚さと不確かさ、それにともなう孤独はヘイ監督のテーマでもあり、この世ならざる存在とは相性がよかったといえる。
-
アダルトビデオ監督 二村ヒトシ
最初ずいぶんスティーヴン・キングみがあるなと思ってたら劇中で言及されてた。〈甘える〉という魂に必要なことを人は大人になったらどこですればいいのさ。さみしさを癒そうとセックスすればするほどさみしくなるし、親と(その親が死んでても生きてても)コミュニケーションなんかしようものなら、ますますさみしくなる。自分は生きてると思ってる我々の営みはすべて、すでに死せる人たちが見ている夢なのだからさみしくてあたりまえだ。大林宣彦版に出た俳優さんたちはもうご覧になったかな。
-
映画評論家 真魚八重子
夕暮れのタワーマンションから見える、ロンドンの星々のような灯りの輝き。美しいと死にたくなる。大林の「異人たちとの夏」は、亡くなった両親が生きている息子の精気を吸い取るような奇妙な話だったが、本作は整頓されている。マンションに二人しか住人がおらず、クィアで美形なため惹かれあうのもわかるが、本作は薬物と強い酒が悲しく付きまとう。孤立したマンションで、訪ねるのも迎え入れるのも遅すぎた。クライマックスのトランス状態で時間が経過するのが上手い処理。
あまろっく
公開: 2024年4月19日-
文筆家 和泉萌香
還暦すぎの男性に自分からプロポーズ(!!)して結婚した美女(つっこみが追いつかないが)……。不器用な独身女と、いまどき「良妻でありたいわ」なんていう若い既婚の女ふたりのキャラクター像に最初うんざりしたが、彼女が「どうしても家族が欲しい」という意思を終始、曇りない笑みで突き通してしまう姿には、思わず頭が下がります。だがありえない設定に盛り込んだ幾つかのエピソードの生々しさが、家族三人白鳥ボートに乗るような、微笑ましいギャグを薄めてしまっている。
-
フランス文学者 谷昌親
尼崎という土地にこだわり、コメディの風味をたっぷり盛り込んだ人情ドラマ、とでも言えばいいだろうか。しかし、ロケーションを活かすというのは、その土地らしい場所で撮影するということではないはずだ。シチュエーションコメディ的な側面のある映画だけに、やや無理のある設定をどう観客に受け入れてもらうかもだいじになってくるわけで、だからこそヒロインの人生を少女時代から描くのだろうが、そのわりには現在と過去のつながりが有機的に感じられないままなのも残念だ。
-
映画評論家 吉田広明
いきなりリストラされたエリート女子と、家族団欒を知らずそれに憧れていた女子が、多幸的老年を鎹として「赤の他人」から本当の家族になるまで。詰まらないわけではないし、血ではなく心情でつながる「家族」という主題の重要性も分かる。しかし、事態の転換点となる場面でのスローの使用はいかにも格好悪いし、いくらやりやすくなったからと言って意味のないドローン撮影も、時間経過、あるいは人物が内向する場面の緩さを音楽でごまかすのも勘弁してほしい(この点、本作に限らず)。
陰陽師0
公開: 2024年4月19日-
ライター、編集 岡本敦史
佐藤嗣麻子監督といえば夢枕獏と谷口ジローのコミック版『神々の山嶺』誕生のきっかけを作った功労者として有名だが、ついに念願かなって「陰陽師」を監督! まずはめでたい。若手キャストを起用し、原作にないエピソード0にするという企画も、狙いとしてはアリである。ただ、作品の根幹たる安倍晴明&源博雅コンビ=山﨑賢人&染谷将太のカップリングに意外とケミストリーが感じられないのは残念。脇を固めるベテラン俳優陣の充実にばかり目が奪われるのは、ちょっともったいない。
-
映画評論家 北川れい子
能楽師の野村萬斎が安倍晴明を演じた「陰陽師」シリーズとは一線を画す、青春映画仕立てにしているのが親しみやすい。若き晴明は、平安朝の慣習や陰陽師なる役職から距離をおき、染まらず流されず合理的に行動、人の心の闇がもたらす不可解な現象や事件に冷静に対処する。という晴明のキャラクターを明確にした上で、佐藤監督は幻視や夢の映像を鮮烈に演出、目が覚めるような華麗な場面も。人物それぞれの立場の野心や思惑も痛快だ。美術や衣裳も見応えがある。
-
映画評論家 吉田伊知郎
以前のシリーズには全く乗れなかったが、さすがに原作への愛着とミステリとVFXに通じる佐藤監督だけあって魅せる。「ヤング・シャーロック ピラミッドの謎」よろしく、若き日の安倍晴明が陰陽師になるための学校に通い、ワトソン役の源博雅と出会って事件に挑むという設定からして愉しい。山﨑、染谷の好演は予想通りだが、帝役の板垣李光人が浮世離れした存在感で目を引く。終盤はVFX頼りになってしまい、そのスケールに予算が追いついていない感が溢れるのが惜しまれる。
プリシラ(2023)
公開: 2024年4月12日-
俳優 小川あん
エルヴィス・プレスリーと初妻プリシラの出会い・結婚・離別までを描く。時系列どおりのノーマルな物語構成。特筆すべきシーンはないのだが、S・コッポラの得意なガールズ・ムービーとしての画作りは深まっている。プリシラの少女性と同時にエルヴィスの少年性が見えたのは新たな発見だった。二人の恋路を眺めていると、エルヴィスに恋をしたような気持ちにさせてくれる。ただ、個人的にバズ・ラーマン監督作「エルヴィス」が前に出てしまったので、本作の印象が少し薄くなってしまった。
-
翻訳者、映画批評 篠儀直子
少女プリシラが飛びこむ状況の異様さは傍から見れば一目瞭然。最初は夢見心地でも、王子様だったエルヴィスはやがて精神的な不安定さゆえに支配欲をむき出しに。女性の自立や尊厳がまだほとんど問題にすらされていなかった時代、彼女はファーストショットで示されたように、自分の足でしっかりと歩けるようになるのだろうか?という話に着地するはずだと思うのだが、最終的にふわっとしてしまうのは、まあソフィアのよさでもあるのだろう。プレスリーの曲がほぼ流れないのも興味深い。
-
編集者/東北芸術工科大学教授 菅付雅信
エルヴィス・プレスリーの元妻プリシラのエルヴィスとの日々を彼女の回顧録をもとにソフィア・コッポラが映画化。保守的な家庭で育った少女プリシラが偶然エルヴィスと出会い、求愛を受けて結婚しスーパースターの華美な館で「籠の中の鳥」のような日々を送る。映画はプリシラの視点で作られ、彼女の「物質的に満たされた空虚さ」を執拗なディテール描写で描く。ソフィア十八番の「お姫様の憂鬱」話だが、もうソフィアの憂鬱ゴッコにうんざり。この空虚さから脱しないと映画作家としてヤバいのでは。
No.10
公開: 2024年4月12日-
映画監督 清原惟
始めと終わりで全く別の映画のように、悪夢のようにさまざまなジャンルを横断していく。とある舞台の座組みの中で起きているドロドロした人間関係の話だと思って観ていると、途中からサスペンスのような雰囲気になり、と思えば最後は異星人SFものになっていた。しかし、すべてに冗談めいた空気があるからか、ジャンルの移り変わりをすんなり受け入れて観られたのが奇妙だった。スケールの大きな話なのにも拘らず、登場人物が最初からあまり変わらず、どこかスモールワールド的な雰囲気も。
-
編集者、映画批評家 高崎俊夫
主人公の舞台俳優と共演者の女優の不倫が発覚し、嫉妬に駆られた演出家である夫が権力を笠に理不尽な報復に出る。前半は至極ありふれた三角関係の行方をサスペンスたっぷりに魅せるが、にもかかわらず、〈監視者〉を介在させつつ意味ありげ、かつ思わせぶりな不条理劇風の演出を施している狙いは奈辺にありや。などと訝しんでいるうちに不意打ちのように訪れる奇想に満ちた展開に?然となる。その壮大なる野心をあっぱれと称賛するか虚仮威しと断ずるかで評価が割れようが、私は後者。
-
映画批評・編集 渡部幻
オランダの変わり種ヴァーメルダムに日本公開された作品は少ないが、71歳のベテラン。「ボーグマン」もかなり風変わりな映画だったが、この新作もそう。幼少期の記憶を持たない役者の物語。田舎劇団に所属し、監督の妻と不倫しているが、悪い人間ではない。アート映画風に淡々と進行、オフビートな喜劇のようだが、面白くなりそうな気配はない。しかし時折、彼を監視するビデオカメラの視点が挿入され……プレスにネタバレ禁止が記されていたが、実際知らない方がよい。監督は観客を信用しているのだ。
氷室蓮司
公開: 2024年4月12日-
ライター、編集 岡本敦史
破格の長期シリーズOV「日本統一」のスピンオフ。台湾ロケを敢行し、誘拐と爆弾テロと復讐劇をミックスした欲張りなドラマが展開するが、節約第一のOVテイストは健在。チープでけっこう、でも悪ふざけはしないという独特の美学は、作り手と常連客の信頼関係ありきのものなので、一見客には敷居の高い世界ではある。大陸におもねる経済ヤクザが登場したり、ひまわり学生運動がキーポイントになったり、独立系ならではの踏み込み方が面白い。80年代末の韓国にもこんな映画あった気が。
-
映画評論家 北川れい子
かつて一般向けの日本映画に背を向けるようにして、任?に生きる男たちやヤクザ世界の抗争などを描き、一部ファンに熱く支持されたVシネマ。当時とは世間も状況も激変したが、本作がその路線で踏ん張っていることに少なからず感心する。しかも今回はドラマ化もされている「日本統一」シリーズ10周年記念作品で舞台は台湾、チラッと台湾の歴史に触れたりも。日本統一を目指す侠和会のナンバー2、氷室の捨て身の父性愛で、話はいささか乱暴だが、それもVシネらしい。
-
映画評論家 吉田伊知郎
ひたすら本宮泰風を愛でてしまう。低温ながら俊敏な動きが際立ち、スター映画の残り香を漂わせる。「日本統一」シリーズが未見でも問題ない作りになっており、台湾を舞台に父子の物語へと拡張させても大味になることなく、ウエットにもならない。爆弾魔の話でありながら合成丸出しの爆発ばかりなのは不満だが、小気味良いアクションを積み重ねて終盤へなだれ込む手堅い演出は好調。東映系のシネコンチェーンで公開されるので、往年のプログラムピクチャーの味わいを愉しむのも一興。
ミルクの中のイワナ
公開: 2024年4月5日-
ライター、編集 岡本敦史
イワナについてのドキュメンタリーと聞いて、ネイチャー番組的なものを想像すると、意外なギャップに驚く。研究者、漁協参事、料理店の主人といった人々のインタビューを通して、イワナを取り巻く現状を多角的に描いていく内容が興味深い。環境問題全体にも関わる多くの示唆も与えてくれるが、だとしても、肝心のイワナの映像が少なすぎる。人間ばかり映しすぎ。鳴りっぱなしの音楽も、スローモーションの美しい映像(それもやっぱり人間主体)も、作品に必要だったかというと疑問。
-
映画評論家 北川れい子
タイトルに使われている言葉の意味を、このドキュメンタリーで初めて知ったのだが、独特な進化を遂げたという渓流魚・イワナのルーツやその現状を記録した本作、実に面白く観た。タイトルにピッタリの知的な詩情とロマンがあり、渓流の流れや水中映像がまた美しい。そしてイワナほかの渓流魚について、さまざまに語る研究者や専門家の方々の、穏やかで分かりやすい言葉。切り口を変えた章仕立ての進行も効果的。ダムには“魚道”があることも今回初めて知った。
-
映画評論家 吉田伊知郎
釣りにもイワナにも興味がない身としては、釣りキチの綺麗事ではないかと斜めに構えて観始めたが、食と生命を真摯に考える人たちの語りに引き込まれていく。大量に釣ってから川へ戻して生態系を維持しましょうなどと言うのは勝手な屁理屈にしか思えなかったが、そうした疑問にも答えてくれる。獲り過ぎて翌日になると魚がいなくなっていた経験を語る宮沢和史が、それを大量殺戮、沖縄地上戦のようと形容することに驚くが、決して大げさではないことがわかるようになっている。
インフィニティ・プール
公開: 2024年4月5日-
映画監督 清原惟
追い詰められた人間の内的世界を覘くような恐さのある作品だった。金持ちが途上国のリゾート地に行って罪を犯しても、お金を積めば自らのクローンに罪を負わせ放免されるという設定は、今の社会を考えると妙なリアリティがあるように思えた。ほとんど語らない主人公の魂が抜け落ちてる感じや、後半のあまりにもグロテスクになっていく展開のやりすぎ感は少々気になったが、クローズアップの際立つ撮影やカット割りによって、土地に流れる時間や、心理描写などが印象深く見えた。
-
編集者、映画批評家 高崎俊夫
ちょっと意地の悪い評言だが、ブランドン・クローネンバーグの映画は異形なる巨人として屹立するフィルムメイカーの父親をいかにアモラルな地平で超克するかという“あがき”のようにも映ずる。異郷のリゾートを舞台に悪無限的に反復される殺戮のセレモニーは、これぞ果敢なるモラルへの侵犯行為と言わんばかりの露骨さだが、島民のF・ベーコン風に歪められた顔貌のイメージと相まって既視感が付き纏う。とはいえ「裸のジャングル」を転倒させたようなモチーフが奇妙な後味を残すのは確かだ。
-
映画批評・編集 渡部幻
ブランドン・クローネンバーグの新作は、アレクサンダー・スカルスガルド(『メディア王』)とミア・ゴス(「Pearl/パール」)を起用して映画的なバネの強さが増している。一見魅惑的な表皮の下に歪で不健全な魂を隠し持つこの2人が体現するのはたがが外れた本能と欲望の極北。不快だが、あまりにも常軌を逸していくので、ひきつった笑いが沸き起こってくる。これは冷血で獰猛な現代の階級風刺。ブランドンに父デイヴィッドの透徹したロマンティシズムは感じないが、独自の生命を宿らせていると思う。
ブルックリンでオペラを
公開: 2024年4月5日-
俳優 小川あん
頑張りすぎると人間は時折疲れる、当たり前のことだ。知らない間に大丈夫になっている、それも然り。スランプに苦しむオペラ作曲家が数奇な巡り合わせから、終盤には元気を取り戻していくハートフルな仕上がりとなっている。今の自分にちょうど良い (素晴らしい意味で) 映画だった。鑑賞後はスッと肩の力が抜けて、さっきまでの悩みがどっかにいってしまう。本作のような肩肘張らない、絶妙なニュアンスの作品が量産されることを願う。そして、疲れたときの散歩はやっぱりいい。
-
翻訳者、映画批評 篠儀直子
軽快なロマコメが急な深刻展開で足を取られたり、そもそも複数のストーリーラインがいっこうにからんでいかなかったりでフラストレーションがたまるのだが、サム・レヴィの撮影の美しさと、クライマックスの大作戦でまあまあアガるのと、オペラ曲とスプリングスティーンの主題歌がいいのとで「まあいいか」という気持ちに。主演として宣伝されているハサウェイがなぜか肝心な局面の前にフェイドアウトしてしまうけど、実質的主役であるP・ディンクレイジと、M・トメイがチャーミング。
-
編集者/東北芸術工科大学教授 菅付雅信
アン・ハサウェイ主演のNYブルックリンを舞台にしたコメディ。精神科医の妻と現代オペラ作曲家の夫の夫婦が主役で、夫は極度のスランプ状態。精神療法の一環で散歩中に出会った女性船長に惹かれ、夫は創作のインスピレーションを得る。長身ハサウェイと小柄なディンクレイジの凸凹カップルのユーモラスなやりとりやNY的多様なキャラでNY讃歌を描こうとしているが、物語のグリップ力が弱い。大都市を舞台にしたスター女優のほんわかコメディという形式がとても色褪せて見える。
毒娘
公開: 2024年4月5日-
文筆家 和泉萌香
「幸せな家族」というが、最初っから夫のモラハラ臭全開で全く幸せそうに見えないのはさておき。人間か、人ならざるものか? 警察の半端な介入描写などがあり、謎めいた少女ちーちゃんの設定と、大人たちの対応があやふやな気もするが、とことん凶暴な彼女が母と妻の座についた従順な女性と、過去の事件で傷を負った娘を「いいカンジの家庭」イメージから引き?がし、文字通り家という籠から蹴りだすさまは荒療治がすぎるが楽しんだ。はらわたをぶった斬る一大流血描写も容赦ない。
-
フランス文学者 谷昌親
ホラーというジャンルは、きわめて映画的と言えるかもしれない。普段なら気にもとめないシーツや壁、窓や扉が画面のなかでにわかに意味を担ってくるからだ。しかし、ホラーという枠組みは諸刃の剣ともなる。恐怖を抱かせるための表現がどうしても紋切り型となり、既視感を呼び覚ますからだ。内藤瑛亮監督が描きたかったのは、むしろ、後妻として家庭に入った萩乃と義理の娘となった萌花が、ともに抑圧から解放され、自律していく過程であったはずだが、それが背景に後退してしまう。
-
映画評論家 吉田広明
毒娘が暴れまわるホラーかと思いきや(まあそうなのだが)、「家族」なるものの偽善を破壊するパンクロックみたいな映画だった。「家族ゲーム」や「逆噴射家族」を思い出した。無論アップデートはされており、「家族」の中でも強者である親にして父が、「同意」による誘導で家族の弱い成員をソフトに抑圧する様は、「家庭」が温かい居場所であるどころか監獄、また強者が弱者を搾取する構造が変えられない今の日本社会の現状を反映している。もう少し人物たちに陰影があっても良かった。
アイアンクロー
公開: 2024年4月5日-
俳優 小川あん
家族愛=プレッシャー。この相関関係は難しい。それが結果、フォン・エリック家の悲劇のファミリー・ヒストリーとして刻まれてしまうのだ。ただ、映画を通して「悲劇」という言葉の背景にある当人しか計り知れない想いを知ることができる。後の世で兄弟が再会を果たすシーンは、緩やかなカメラワークに温かな自然光が差し込み、本筋より現実味があった。ケヴィンの結婚パーティーで「今だったら家には誰もいない」とちゃっかり抜け出そうとする長年の夫婦の愛が垣間見えるシーンが好き。
-
翻訳者、映画批評 篠儀直子
弟がひとり減らされているなど事実とは異なる点も多いようだが、日本の80年代プロレスブームのころの人気レスラーが次々登場するだけでもオールドファンは興奮必至。ロックスターみたいに美しい4兄弟を描き分けながら快調に進行する前半には「ボヘミアン・ラプソディ」的なよさがある。一方、対戦相手を踏みつけるフリッツの表情が大写しとなるタイトルバックは、これが「父の抑圧」の物語であることを宣言しているように見えるのに、後半そのあたりが曖昧になっていくのが不思議。
-
編集者/東北芸術工科大学教授 菅付雅信
70~80年代に活躍したプロレスラーで必殺技“鉄の爪=アイアンクロー”を持つフリッツ・フォン・エリックと彼の四人の息子レスラーたちのプロレス家族の実話映画化。圧倒的な強く正しい父の下で、息子たちはプロレス道を邁進するも、心も体も蝕まれていく。映画は長男ケヴィンを軸に描かれ、彼のエディプス・コンプレックスが物語の通奏低音になっており、フィルム撮影による拡張高いルックも相まって、プロレス版「ゴッドファーザー」といった趣。しかし善悪の彼岸を垣間見せるほどの哲学的深みはない。
リトル・エッラ
公開: 2024年4月5日-
文筆業 奈々村久生
好きなものにだけ囲まれていたい、そうじゃないものとは関わらなければいい。そんなシンプルな世界に生きていたはずのズラタン(エッラ)が、大好きな人の恋人という存在に向き合うのは、自分と違う「他者」を尊重し受け入れる体験に他ならない。子どもらしい発想を駆使したユーモラスな演出でラッピングされているとはいえ、彼女がその現実を知らなければならないことを思うと切なくなる。これをしっとりといい話ふうにせず、ズラタンの感情や衝動のパワーに寄り添った見せ方が心地よい。
-
アダルトビデオ監督 二村ヒトシ
友だちがいないから恋愛ばかりしてる人も、好きになってはいけないことになってる人を好きになる人も、不潔でグロテスクってことになってる小動物が親友な人も、誰がしたのかわからぬ大便と対話する幼女(エッラや、Dr.スランプのアラレちゃん)も存在する。みんな反道徳的かもしれないが非倫理的ではない。嫉妬は嫉妬する人自身を苦しめるから、幼い人が嫉妬してたら大人はその幼い人を愛さなくてはいけない。心が幼い人に対しては欲望は向けず、愛することだけをしなければならない。
-
映画評論家 真魚八重子
確かに子どもにとって、休暇を唯一好きな親戚のおじさんと楽しめないのは残念なことだ。だが子どもが嫉妬から行う悪戯によって、大人たちが恋愛関係に終止符を打ったりするのは、真に受けすぎている。その子が後々大人になって自分のやったことを思い返したら、生きた心地がしないんじゃないだろうか。外国人で言葉が通じないとか、美術館の安っぽいアートなど、古典的ギャグがキツかった。一番魅力的なキャラクターは転校生のオットーだ。彼の暗いが一途な佇まいは存在感がある。
ゴッドランド GODLAND(2022)
公開: 2024年3月30日-
映画監督 清原惟
ふしぎな夢を見ているような感覚だった。寒い土地の話だけれども、画面の隅々までいつも光があたっているような、独特の色彩がうつくしい。厳密に計算して撮影されたフレーミング、芝居だと思うが、にもかかわらず人々の生活はまるで目の前で本当に繰り広げられているような説得力がある。傍観するようなカメラも、けっして突き放すわけでもなく寄り添うわけでもなく、この土地の匂いや湿度、そして時間そのものを捉えようとしているように感じ圧倒された。犬がとにかくかわいかった!
-
編集者、映画批評家 高崎俊夫
デンマーク人の若い牧師ルーカスがかつての植民地アイスランドの辺境の村へ教会を建てる命を受け、旅立つ前半は過酷な自然に脅かされる受難篇。後半は村の教会が完成するまでの牧歌的かつ不穏な日々が描かれる。ダゲレオタイプに想を得た村人たちの肖像写真が印象深いが、腐蝕する事物たちの定点観測は実験映画的だ。とりわけ二人の姉妹が室内で佇むシーンはその陰影の深さにおいてカール・ドライヤーに影響を与えた画家ヴィルヘルム・ハマスホイの人物画を想起させるすばらしさである。
-
映画批評・編集 渡部幻
19世紀末、デンマーク統治下のアイスランドに派遣された若い牧師。教会を建て、布教するためだが、彼の理想と支配者側の傲慢さは厳しい自然に囲まれた現実の生活に押し潰されていく。旅を描いた前半部の目の眩むロケーション撮影と流れるような映像の絵画は、ヘルツォークを彷彿とさせるほど壮大で、同時にライカートやフォードの西部開拓劇、「ミッション」「沈黙」を思い出したが、神々を知覚させる自然環境の描写は、アイスランドの山々が人の営みを見下ろす「LAMB/ラム」をむしろ連想してもいた。
美と殺戮のすべて
公開: 2024年3月29日-
文筆業 奈々村久生
アウトサイダーカルチャーのシーンと製薬会社の過失を記録した志の高さは認めるが、映像によって語る行為において、自分が映画という表現に求めるものとは異なると言わざるを得ない。メインの被写体であるナン・ゴールディンの写真がスライドショー形式で上映されるのを彷彿とさせるような画づくりは、テーマありきで構成され、ビジュアルや言葉はそれを裏づける資料として機能する。ゴールディンの実像もその筋書き以上には見えてこない。題材と手法が必ずしも比例しないのは悩ましい。
-
アダルトビデオ監督 二村ヒトシ
世界から痛めつけられている。生きているだけで痛い。〈普通〉じゃない私だけの痛み。痛みがあるから芸術を創作し、痛みがあるから恋愛する。鑑賞者の痛みを刺激して感動される。痛い恋愛してるから殴られて眼底骨折する。痛いから戦える。痛いから何らかの依存症になる。痛みなんかないほうがいい。痛みを消してくれる危険な薬物を大量生産して人を殺して儲ける〈普通〉の人非人。ナンは言う。「売春していたことは初めて話した。売春は恥ずかしい仕事ではない。けれど、楽な仕事でもない」
-
映画評論家 真魚八重子
ナン・ゴールディンが仲間と、サックラー家が販売製造し中毒者を多く出している「オピオイド系鎮痛剤」に反対運動をしている。映画はナンの過去を振り返り、むしろ80年代にはLGBTQの人々が集まる店で働き、ドラッグサブカルチャーの写真を撮っていたことを語る。被写体の多くをエイズで失ってしまったことも。自己判断で麻薬をやることと、医師の処方箋によってオピオイドの中毒になるのはあまりに違う。それは謎の病気だったエイズが自己判断の死でなかったことと一緒なのだ。
RHEINGOLD ラインゴールド
公開: 2024年3月29日-
映画監督 清原惟
実在するラッパーの自伝を基にした映画。ヨーロッパの移民のコミュニティ意識についての描写は興味深かったが、ともかく主人公の人生が嘘みたいな展開をしていくので、現実にこういうことが起きていたとはなかなか思えない。強盗をして入れられた刑務所で、ふいに子どもの頃を思い出し、机にピアノを描いて弾くシーンでは、彼の本当の姿がようやく見えたような気がした。このシーンがよかったからか、最後いろいろな描写をすっとばし、成功者になっている展開には、やや違和感も感じた。
-
編集者、映画批評家 高崎俊夫
これが実話の映画化とは驚く。ファティ・アキンは「女は二度決断する」の冷徹な復讐鬼と化したヒロインが記憶に残るが、この映画ではクルド系のエリート音楽家の家に生まれたカターが街の不良に半殺しの目に遭い、ボクシングを学んで一矢を報いるエピソードにデジャ・ヴ感あり。ドラッグの売人に身を落とすも刑務所内で作った曲が大ヒットという古典的なジェットコースター風の貴種流離譚でもある。ラップのリズムがいつしか映画の鼓動そのものへと同調する辺りが実にスリリングだ。
-
映画批評・編集 渡部幻
イラン系クルド人の両親をもつクルド系ドイツ人ラッパー“Xatar”の半生に基づく青春・犯罪・音楽ドラマ。1979年に始まり第一次湾岸戦争を通過してドイツを経由し、アムステルダムに辿り着く多言語の物語。主人公の背景も複雑だが、トルコ系ドイツ人監督のアキンは「グッドフェローズ」風の年代記スタイルで手際よく捌く。マイノリティとギャングはアメリカ映画の十八番だったが、ここでは欧州でのクルド系に応用されており、それもハッピーエンド。中身は新鮮。だが容れ物はそうでもないのだ。
オッペンハイマー
公開: 2024年3月29日-
俳優 小川あん
クリストファー・ノーランがこれまで描いてきた宇宙物理学が歴史上の重要人物に点火した。真正面からオッペンハイマーと向き合ったノーランの映像作家としての極意が明らかになったように思える。まさに、素粒子のように思考を凌駕するほどの情報が飛び交い、人間の心理に爆発的なエネルギーが集まる。そして人物像が形成されていく! この手法に“65mmカメラ用モノクロフィルム”という最新技術が加わるのだから……。これほどの映画体験を味わうと、もう後戻りできない。
-
翻訳者、映画批評 篠儀直子
決してわかりやすい構成ではなく、カタルシスが得られるわけでもないこの映画があれほど大ヒットした理由は、いま一度多面的に考察されるべきだろう。筆者はノーランのあまりよい観客ではなく、基本的に「脚本の人」だという考えはいまも変わらないが、原爆投下後、オッペンハイマーがチームに向けてスピーチをし、会場をあとにするまでのシーンの演出のマジックは圧倒的。ノーランが置かれている状況では、この演出でメッセージを表現するのが精一杯だったということでもあろうけど。
-
編集者/東北芸術工科大学教授 菅付雅信
原子爆弾を開発した天才物理学者オッペンハイマーの栄光と没落。NHK Eテレの教育番組で終わりそうな地味でハリウッド映画的でない題材を、ノーランは持てる力を存分に注ぎ込んで圧巻のスペクタクルな映像・音響体験に仕上げた。ノーランの最高傑作とは思わないが、ノーランの映画作家力をこれほどまでに感じるものはない。そして映画の普遍的な主題は、超越的な力の獲得がもたらす非喜劇と時間=歴史の捉え直しであることを再認識。ノーラン自身が映画体験のマッド・サイエンティストなのだ。
ナチ刑法175条
公開: 2024年3月23日-
翻訳者、映画批評 篠儀直子
20年以上前の傑作がデジタル・リマスターを機に劇場公開。出演してくれた証言者たちがいまでは全員鬼籍に入っていることを思うと、この作品の意義は一層大きくなる。彼らの人生には、当たり前だがひとつとして同じものはなく、事態を多面的に見せてくれると同時に、このほかにも膨大な数の人生が失われたことを思い知らされて愕然とする。ここで語られる事態が、自由と寛容の頂点というべきワイマール時代の直後に訪れたという恐ろしさ。「人々はすぐ無関心になる」という言葉の重さ。
-
編集者/東北芸術工科大学教授 菅付雅信
ドイツで施行されていた同性愛を禁じる「刑法175条」を題材にしたドキュメンタリー。特にナチス支配下で男性同性愛者は激しく弾圧され、収容所に送られたという。そのわずかな生存者に迫る本作は、かなり高齢となったサバイバーの鮮烈な体験談を収める。ゲイ、ナチス、強制収容所と強い題材であるにもかかわらず、映画はあまり工夫のない淡白な出来。貴重な証言を世に伝えることが主眼であれば、映像よりもノンフィクション小説に仕上げたほうが良かったのでは。
-
俳優、映画監督、プロデューサー 杉野希妃
ナチが同性愛者を迫害していたという事実をはじめて知った。壮絶な過去を持つ人間が数十年後にその体験を語ってほしいと言われても、そう簡単には語れないだろう。言葉をつまらせ涙を浮かべながら明かされる、彼らが受けた拷問や人体実験の数々。語りたい/語りたくない想いの狭間で引き裂かれる彼らの苦悩と、聞くことを躊躇する若い聞き手の葛藤。歴史を掘り返す双方の勇気が描かれていた。「人間はすぐに無関心になる」という劇中の言葉は真実だけれど、それに抗おうとする真摯な映画。
流転の地球 太陽系脱出計画
公開: 2024年3月22日-
文筆業 奈々村久生
『三体』の劉慈欣による短篇小説を映画化したシリーズ2作目だが、前作ともども原作の面影はほぼ見当たらず。序盤の怒濤のアクション描写とコメディ色が謎すぎる。SFでありながら作劇、メッセージ、映像的にも目新しさはない。それどころか地球の未来を担う各国首脳陣や意思決定のポジションには男性の姿ばかりが集結するという前時代ぶり。全体主義的な自己犠牲の精神性を讃えるような文脈にも危険を感じる。ただし、アンディ・ラウの芝居と彼のパートには一見の価値が残っている。
-
アダルトビデオ監督 二村ヒトシ
地球自体にエンジンつけて太陽系を脱出する計画の訓練生が恋愛しながら軌道エレベータで宇宙に向かってたら、人類全員が意識をコンピュータに移植して電脳空間で精神体になって生きのびるべきだという思想のテロ集団に襲撃され、スター・ウォーズ的ドッグファイトとCG多用の格闘。すでにお腹は一杯だし、そこからさらに2時間半延々と続くSFギミックと泣かせ演出の連発、そのすべてに既視感。原作は未読ですけど短篇で傑作だというから、きっとギュッと圧縮された〈詩〉になってるのだろう。
-
映画評論家 真魚八重子
原作は未読。またシリーズものと思わず1作目も未見。そのためか本作は3時間の大作であるにもかかわらず、突然始まった早回しのダイジェストを観ているようで、恥ずかしながらほとんど意味がわからなかった。全世界で協力して「妖星ゴラス」をするのだろうか。途中でアンディ・ラウが出てきてようやくホッとした。彼と幼い娘のやりとりは悲痛で狂気に浮かされたようなエモーションがあり、ようやく映画らしい瞬間を観た気がした。星はわたしが怠惰な状態で観たのを差っ引いてください。
コール・ジェーン 女性たちの秘密の電話
公開: 2024年3月22日-
文筆業 奈々村久生
60年代アメリカを舞台とした物語だが、ノスタルジーとは無縁な16mm映像の等身大レトロルックは、時代劇とは思えない手触りで当時の復刻版かと錯覚してしまうほど。E・バンクスの馴染み方も素晴らしい。特に堕胎に臨む女性の心理、施術室の様子、手順の過程までつぶさに追った描写は秀逸で、数々の映画で感動的にフィーチャーされてきた出産シーンと同じように、今後も描かれていくべきだ。終盤の展開はやや飛躍して見えるが、荒唐無稽な寓話より圧倒的にエッセンシャルな一本。
-
アダルトビデオ監督 二村ヒトシ
彼女はホテルの宴会場で華やかな、つまらないパーティに出ていた。ホテルのすぐ外では反ヴェトナム戦争のデモ。他人の痛みは自分の痛みではない。だが、そう感じてしまった人間を運命は逃さない。堕胎しないと生きていくことができなくなって初めて、この社会の宗教と道徳は堕胎を許さないことを知る。そうなって初めて出会える人がいる。立場が異なる者たちが同じ立場で戦うとき友情が湧く。お元気そうなシガニー・ウィーバーを見て、僕は「嬉しい、また会えた」という気もちになりました。
-
映画評論家 真魚八重子
1960年代、中絶が違法だった時代のアメリカで、一般の女性たちが自分の身体の権利のために、中絶手術を行う極秘の活動を繰り広げる。主演のエリザベス・バンクスは「コカイン・ベア」の監督もすれば、中流家庭の専業主婦の役もこなす、信頼のできるクリエーターだ。この団体の中心人物がシガニー・ウィーバーなのも、圧倒的な頼り甲斐しかない。良い話過ぎるきらいはあるが、この時代に戻るかもしれない切羽詰まった現状では、初歩的な問題をわかりやすく振り返る映画も必要だろう。
ペナルティループ
公開: 2024年3月22日-
文筆家 和泉萌香
人生という牢獄のなかでいかに生きるか?「恋はデジャ・ブ」はじめ数々の傑作があるループもの。本作は恋人を殺害した男に復讐する一日を何度も繰り返す、というものだが、復讐の方法もターゲットを殺害一択、パターンもほぼ同様、まず復讐とはいえ「殺人」をおこなう主人公の精神面はいかなるものかと注目するも、それへの掘り下げも浅薄、加害者との関係のうつろいもふやけ気味。生や死がどうにも軽く、ただの仮想世界での「ゲーム」的な空虚さが残ってしまう。
-
フランス文学者 谷昌親
ループものかとやや腰が引けたが、ちょっと様子が違うと気づいたころには作品世界に引き込まれていた。とはいえ、並のループものとは違うというだけなら底の浅い映画になっただろう。主人公の岩森が黄色いコンパクトカーで走る道、夜の深い闇と暗い水面の反映、工場の庭にそびえる木といったなにげない要素がこの作品に艶をもたらしている。ループが終わったあとに聞こえてくる鳥の声と雑踏の音も魅力的だ。いろいろと仕掛けがありながら隙間が残っているのもこの作品の美点。
-
映画評論家 吉田広明
何度も死(私)刑を繰り返すVRという発想、主人公と犯人が意に反して仲良くなる展開は興味深いが、ただし犯人の動機、贖罪や死刑制度といった問題には踏み込まず、それはそれで選択、映画に「問題」など必要ないのかもしれない。ただ結局何も変わらなかったかのように見える結末はどうか。主人公に内的変化はあったはずで、それを体感するには彼と犯人の時間が、それだけで映画的時間でありうるほど充実すべきで(犯人の絵がそこで生きるのでは)、それ次第で結末も変わってきたはず。
四月になれば彼女は
公開: 2024年3月22日-
ライター、編集 岡本敦史
今の世の中で「生きづらさ」と「解放」を描くなら、こういう話じゃなくない?という違和感が拭えず。恋愛や結婚に生きづらさを覚えている主人公たちがいて、しかし映画としては恋愛成就を帰結とするジャンルムービーなので、矛盾は当然生じる。その矛盾を突破するべきドラマに、強度も説得力も感じられない。彼らが完全に恋愛から解放される瞬間がないからだろうか。後半の展開はホラー映画にも転用できそうで、介護職員の人材不足という問題は痛いほど伝わる内容ではある。
-
映画評論家 北川れい子
失うのが怖くて愛に臆病な恋人たちの10年越しの因縁メロドラマだが、国内ロケでも辺鄙な場所を選べば十分通用する話を、わざわざ異国の絶景でロケ、いやその絶景は確かに素晴らしいが、だからといって話が広がるわけでもない。原作者の川村元気としては、恋愛や結婚にいまいち消極的だという世代の一面を描いたのだろうが、未練と感傷の遠回り、君たち、本気で愛したの? いつもテキパキ颯爽とした長澤まさみが、獣医役はともかく、こんな曖昧な行動をするのもいかにも嘘っぽい。
-
映画評論家 吉田伊知郎
手紙を読む森七菜の柔らかな声と共に、彼女がプラハ、アイスランドなど各地を歩く姿に瞠目する。まるで佐々木昭一郎のドラマを観ているかのような美しさに魅せられたからだ。都内の何気ない風景も繊細に映し出し、中島歩、河合優実を脇に配した配役も申し分ない。映像技巧に走らず、じっくり芝居を捉えるのも好感を持って観ていたが、失踪していた長澤まさみの謎が明かされると、単に自分がすっきりしたいだけの自己満足的行動かつ、ストーカーめいた真似をしているので白けてしまう。
映画おしりたんてい さらば愛しき相棒(おしり)よ
公開: 2024年3月20日-
ライター、編集 岡本敦史
あられもないビジュアルで子どもに大人気のキャラクターだが、見た目ほど品のないギャグは少ないので親御さんは安心して家族で観に行ってほしい。むしろ節操のなさでは「劇場版 SPY×FAMILY CODE:White」のほうが遙かに上だった。密偵アクション風のストーリーはたわいもないものだが、終幕には大画面にふさわしく特大の一発を浴びせてくれる。りんたろう監督版「メトロポリス」の超巨大ビルと「スチームボーイ」のエフェクト作画が合体したようなクライマックスは一見の価値あり。
-
映画評論家 北川れい子
子どもたちに人気というこのアニメを観たのは今回が初めてだが、かなり感心した。人間や動物たちが混在するキャラクターは確かに児童向きだが、どうしてどうして大人でも楽しめる。まぁ当然だろう。テレビアニメと違って児童が劇場版を観に行く場合、大人同伴も少なくない。とあればキャラはともかく雑なドラマは許されない。そもそも“さらば愛しき相棒よ”というサブタイトルからして大人向き。お尻顔の探偵が、隠し球というか、黄色の切り札!を乱発しない節度にも感心する。
-
映画評論家 吉田伊知郎
1歳の息子とTV版を見ているため、本欄で担当するアニメとしては珍しく(失礼!)予備知識があった本作。もっとも昔の相棒との馴れ初めが発端になるため一見さんでも問題なし。中心となる元相棒との再会と、贋作絵画すり替え事件の?末も目新しさはないが飽きさせない。陰のあるキンモク先生を奥行きのある声の演技で聴かせた津田健次郎に引けを取らなかったのが、元相棒スイセン役の仲里依紗。声優としての出演作は少ないものの、その声を高く買う者としては今回の役は絶品。
戦雲 いくさふむ
公開: 2024年3月16日-
文筆家 和泉萌香
棄民亡国、の四文字がぴったりな国だ。三上監督もおっしゃる通り、喜怒哀楽の真ん中の二文字、怒と哀ばかりが胸を占める。「こうやって、私たちを疲れさせようとしている」……。住民の方々の反対、抵抗運動のあと、淡々と画面に現れる数年後の数字。繰り返される叫びの圧殺。だが、よく簡単に「絶望」と言ってしまう私は自分を恥じた。映画に登場する方々の声、皆の祈りが、この2時間が過ぎたあとも、さらにつらなり、さらに大きな祈りにするために、広く上映されることを切望する。
-
フランス文学者 谷昌親
沖縄の厳しい状況は、それなりに理解しているつもりでいたが、「戦雲」を観ると愕然としてしまう。南西諸島に次々と自衛隊の基地が作られ、ミサイル配備が着々と進んでいるのだ。沖縄の植民地化にほかならず、同時に、日本そのものがいつのまにか臨戦態勢に置かれている……。三上智恵監督の執念を感じさせる取材の結晶だが、基地問題ばかりでなく、与那国島でのカジキ漁など、南西諸島に住む人びとの日々を描くことで、このドキュメンタリー映画に作品としての厚みももたらしている。
-
映画評論家 吉田広明
台湾有事を口実に着々と軍事基地化されていく沖縄、南西諸島の現状報告。既成事実で住民を疲弊させる自衛隊=政府、住民投票さえなかったことにして追従する地方議会。実際の有事に備え隊員用シェルターは用意するが、住民避難は保証しない。この島々の住民を守れない/守る気がないとは、つまり日本国民を守れない/守る気はないということだろう。「もしトラ」になれば米は棄日、梯子を外されて矢面に立たされた日本国の棄民は現実化する。思想なき国防が招く末路を考えさせる一作。
薄氷の告発
公開: 2024年3月15日-
文筆業 奈々村久生
スポーツ界における師弟関係を利用した性加害が次々と明るみに出てくる中、そこに切り込んだ制作の心意気は買う。が、これは現在進行形で取り組まなければならない切実な問題であり、社会的な制裁が被害者個人の魂を救うとは限らない。それに対してこの脚本や演出はあまりにも事態を単純化しすぎており、被害者と加害者の人物造形や演出も、複雑な現実に対応するきめ細やかさを携えているとは言い難い。性犯罪がいかに一人の人間を破壊するのか、ラストはせめてもの誠意として受けとめたい。
-
アダルトビデオ監督 二村ヒトシ
現実の事件についてこういう話をすると「加害者を甘やかすな」と批判されることがあるのでこの映画についての話としてするけど、むろん第一に必要なのが被害者の心のケアであるのは当然として、同じくらい重要なのが加害側の心の治療だ。この映画の犯人はパワハラと性的暴行をしないでは生きてる実感がわかない〈死んだ魂〉の持ち主なので服役しながらカウンセリングを受ける義務があるし、この映画に登場する加害側の人間全員にも、あなたはじつは心の病気なのだと教えるべきだと思う。
-
映画評論家 真魚八重子
韓国スケーター界の、パワハラ、セクハラと脅迫の犯罪行為を取り扱った映画で、最悪の結果を想定したストーリーである。被害の経験者が、これから被害に遭うかもしれない状況の女性に対して、自分の過去を口にできず、茫漠とした説明しかできないのもわかる。そういった口が重くなる羞恥や苦痛も含めての加害行為なのだ。被害を立証する難しさや、加害者側が有利に立ち回りやすい案件であることも本作は証明する。日本の映画業界も同様の最悪の結果が続き、非常に腹立たしい。
RED SHOES レッド・シューズ(2023)
公開: 2024年3月15日-
翻訳者、映画批評 篠儀直子
プロットが穴だらけなのはひどいが、カンパニー内や友人同士の信頼の大切さと、「踊らずにいられない」表現者の思いの切実さを描いているのがとてもいい。心情を語るような歌詞の曲に合わせて主人公らがモダンバレエを踊るので、「フットルース」的な青春疑似ミュージカルの趣も。本物の実力者がそろっているからダンスはみな素晴らしく、クライマックスの公演シーンは、撮り方の成否はともかく、パウエル&プレスバーガーの名作と並んでも恥じないものをという作り手の気概を感じる。
-
編集者/東北芸術工科大学教授 菅付雅信
オーストラリアの若きバレエダンサーの物語。姉の事故死のショックに立ち直れずバレエを引退した少女が、バレエ学校で清掃員として働きながらも夢を捨てきれず、再びバレエに取り組む。ほとんどC級少女漫画のような設定で脚本は0点に近いのだが、実際にバレエをやっている人たちをキャストしているだけに、バレエ・シーンは見事。俳優たちがバレリーナを演じた「ブラック・スワン」と比較するとバレエ・シーンの迫力が段違い。いっそ物語パートを省いたヴァージョンを見たい。
-
俳優、映画監督、プロデューサー 杉野希妃
トラウマと向き合い、自己表現を追求する物語は胸を打たれるものだが、本作は肉親の喪失や友人とのすれ違いが深く掘り下げられないまま、既視感満載なエピソードが次から次へと積み重なってゆくので、感情移入しにくい。現代的な側面を強調したいという意図のもと、クラシック音楽の合間に頻繁に流されるポップソングは、人物の感情に表層的に寄り添っているだけだ。とはいえ、バレリーナでもある主演のドハーティは憂いを帯びた表情が美しく、そのしなやかな筋肉のキレには息をのむ。
ビニールハウス
公開: 2024年3月15日-
映画監督 清原惟
ビニールハウスに住むというのが、「半地下」のことを思い出したり、韓国の賃貸事情について思い巡らせられた。途中までは、主人公の女性のメンタルヘルスの問題や、盲目の認知症の老人との関わりなど、スリリングな心理描写に惹きこまれたが、人が死んでから、グロテスクで既視感のある映画的展開になっていき、もうこういうのはいいかなと思ってしまった。それまでの時間も、すべてこの展開のためのものに感じてしまう。人の不幸を見て喜ぶ感覚が、自分にはわからないからかもしれない。
-
編集者、映画批評家 高崎俊夫
かつてイ・チャンドンの秀作「バーニング 劇場版」では荒涼たる田園地帯に点在するビニールハウスの光景が何とも形容しがたい寂寥を感じさせた。だが、本作ではさらに韓国の格差社会の暗喩としてのその存在が徹底化、象徴化されて描かれる。疲弊したヒロインに巣くう絶えざる自己懲罰の衝動と少年院にいる息子への溺愛、そして著しく根拠を欠いた彼女の夢想が無惨に打ち砕かれるさまを、映画は時には仮借なきまでにリアルに、時には詩的で幻想的なビジョンをもってあぶり出している。
-
映画批評・編集 渡部幻
冒頭のビニールハウスでイ・チャンドン「バーニング 劇場版」を、続く母と息子の対話場面で黒沢清「CURE」を連想。いきなり今でも有名な別の何かに似ていたため、この新鋭の志に軽く失望したが、これから始まるドラマの悪夢的なトーンを予告する役割を担わせたのだろう。事実、訪問介護士と貧困を背景とする社会的孤立の物語は雪だるま式に悪化する。キム・ソヒョンの芝居に緊張感があり、イ・ソルヒは脚本と編集も兼ねることで重く憂鬱なリズムとテンポを維持している。少し硬いが意欲作だとは思う。
スケジュールSCHEDULE
 映画公開スケジュール
映画公開スケジュール
- 2024年4月19日 公開予定
-
劇場版ブルーロック EPISODE 凪
TVアニメ、アプリゲーム、舞台など多方面で展開された人気サッカーシリーズ初の劇場版。300人の高校生フォワードたちが世界一のストライカーを目指す“ブルーロック(青い監獄)”での戦いを、桁外れのサッカーセンスを持つもうひとりの主人公・凪誠士郎の視点から描く。島崎信長、内田雄馬、興津和幸、浦和希らがTV版と同じ役で声の出演。監督はTV版で副監督を務めた石川俊介。 -
METライブビューイング2023-24 ヴェルディ「運命の力」
ニューヨーク・メトロポリタン劇場で上演されるオペラを、インタビューなどを交えて上映するシリーズ2023-2024シーズンの1本。運命の力に翻弄される恋人たちの逃避行を描いたヴェルディの傑作オペラを、舞台を戦時下の現代に移した新演出で上演。演出は映画監督出身で、「METライブビューイング2016-17 ワーグナー『トリスタンとイゾルデ』」を手がけたマリウシュ・トレリンスキ。出演は、「METライブビューイング2022-23 R・シュトラウス『ばらの騎士』」のリーゼ・ダーヴィドセン。 -
陰陽師0
実在した最強の呪術師・安倍晴明が陰陽師になる前の知られざる学生時代を描く呪術エンタテイメント。陰陽寮の学生・晴明は、呪術の天才ながらも陰陽師に興味がなく、授業もサボってばかり。そんな中、貴族の源博雅から皇族の徽子女王を襲う怪奇現象の解決を頼まれる。若き日の安倍晴明を「キングダム」シリーズの山崎賢人、源博雅を「最初の晩餐」の染谷将太、徽子女王を「マイ・ブロークン・マリコ」の奈緒が演じる。監督は「アンフェア」シリーズの佐藤嗣麻子。