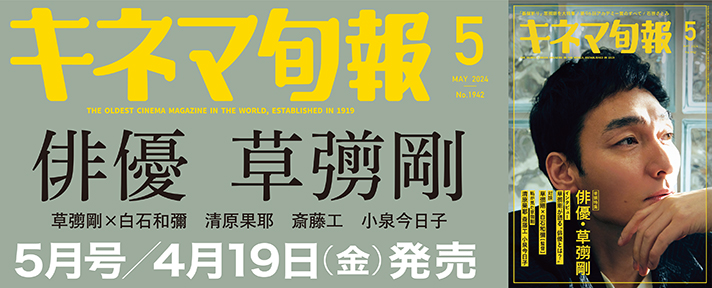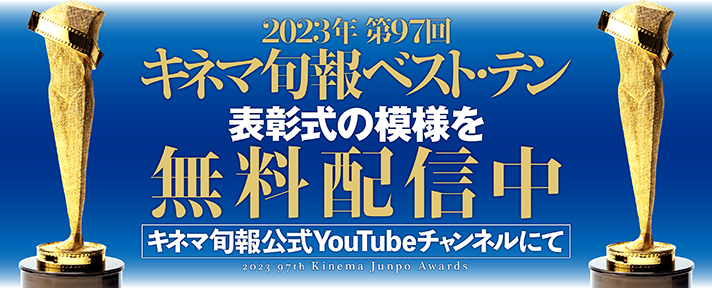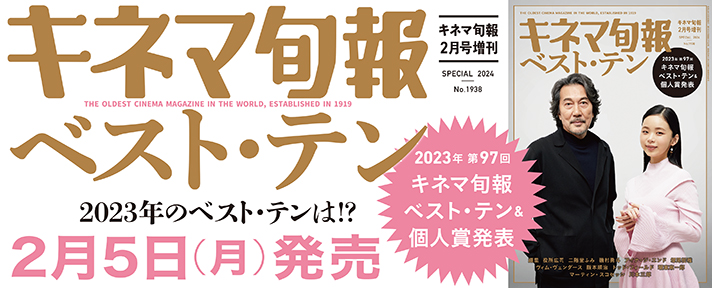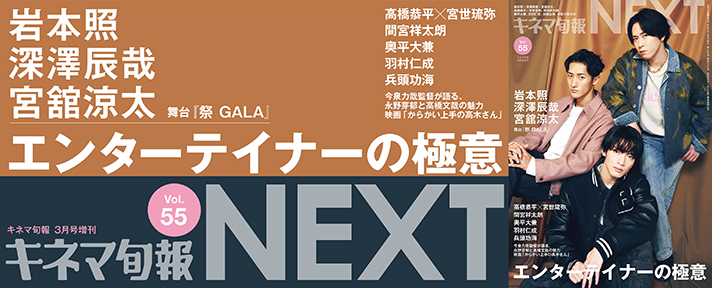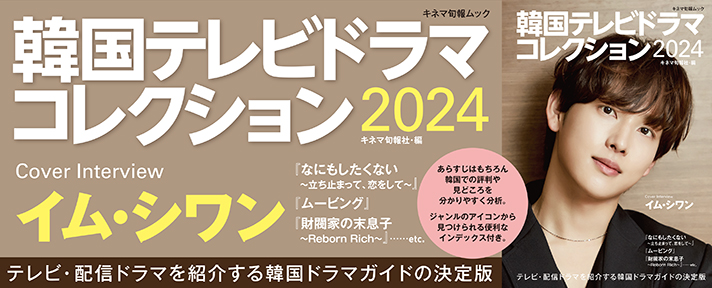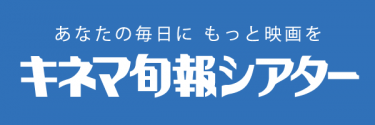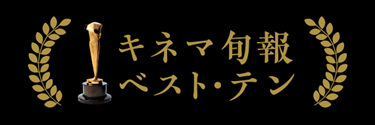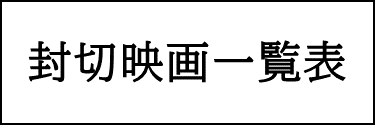映画専門家レビュー一覧
-
青春(2023)
-
映画批評・編集
渡部幻
ワン・ビンは中国経済の一翼を担う長江デルタ地域の出稼ぎ労働者たちの特異な環境を捉え、文字では到底伝わらないだろう生活臭を充満させる。灰色の衣料品工場にミシン。灰色の空、灰色の生活、室内も室外もゴミだらけだ。カメラは若者たちを追う。みんなタバコを吸い、カップ麺を食べる。会話の中心は恋、妊娠、結婚、そして賃上げの交渉。肉体的な距離が密接で、やたらにじゃれ合う。ぼくに身近な20世紀後半の日本を思い出したが、彼らの手にはスマホが握られている。これもまた“21世紀の青春”なのだ。
-
-
陰陽師0
-
ライター、編集
岡本敦史
佐藤嗣麻子監督といえば夢枕獏と谷口ジローのコミック版『神々の山嶺』誕生のきっかけを作った功労者として有名だが、ついに念願かなって「陰陽師」を監督! まずはめでたい。若手キャストを起用し、原作にないエピソード0にするという企画も、狙いとしてはアリである。ただ、作品の根幹たる安倍晴明&源博雅コンビ=山﨑賢人&染谷将太のカップリングに意外とケミストリーが感じられないのは残念。脇を固めるベテラン俳優陣の充実にばかり目が奪われるのは、ちょっともったいない。
-
映画評論家
北川れい子
能楽師の野村萬斎が安倍晴明を演じた「陰陽師」シリーズとは一線を画す、青春映画仕立てにしているのが親しみやすい。若き晴明は、平安朝の慣習や陰陽師なる役職から距離をおき、染まらず流されず合理的に行動、人の心の闇がもたらす不可解な現象や事件に冷静に対処する。という晴明のキャラクターを明確にした上で、佐藤監督は幻視や夢の映像を鮮烈に演出、目が覚めるような華麗な場面も。人物それぞれの立場の野心や思惑も痛快だ。美術や衣裳も見応えがある。
-
映画評論家
吉田伊知郎
以前のシリーズには全く乗れなかったが、さすがに原作への愛着とミステリとVFXに通じる佐藤監督だけあって魅せる。「ヤング・シャーロック ピラミッドの謎」よろしく、若き日の安倍晴明が陰陽師になるための学校に通い、ワトソン役の源博雅と出会って事件に挑むという設定からして愉しい。山﨑、染谷の好演は予想通りだが、帝役の板垣李光人が浮世離れした存在感で目を引く。終盤はVFX頼りになってしまい、そのスケールに予算が追いついていない感が溢れるのが惜しまれる。
-
-
あまろっく
-
文筆家
和泉萌香
還暦すぎの男性に自分からプロポーズ(!!)して結婚した美女(つっこみが追いつかないが)……。不器用な独身女と、いまどき「良妻でありたいわ」なんていう若い既婚の女ふたりのキャラクター像に最初うんざりしたが、彼女が「どうしても家族が欲しい」という意思を終始、曇りない笑みで突き通してしまう姿には、思わず頭が下がります。だがありえない設定に盛り込んだ幾つかのエピソードの生々しさが、家族三人白鳥ボートに乗るような、微笑ましいギャグを薄めてしまっている。
-
フランス文学者
谷昌親
尼崎という土地にこだわり、コメディの風味をたっぷり盛り込んだ人情ドラマ、とでも言えばいいだろうか。しかし、ロケーションを活かすというのは、その土地らしい場所で撮影するということではないはずだ。シチュエーションコメディ的な側面のある映画だけに、やや無理のある設定をどう観客に受け入れてもらうかもだいじになってくるわけで、だからこそヒロインの人生を少女時代から描くのだろうが、そのわりには現在と過去のつながりが有機的に感じられないままなのも残念だ。
-
映画評論家
吉田広明
いきなりリストラされたエリート女子と、家族団欒を知らずそれに憧れていた女子が、多幸的老年を鎹として「赤の他人」から本当の家族になるまで。詰まらないわけではないし、血ではなく心情でつながる「家族」という主題の重要性も分かる。しかし、事態の転換点となる場面でのスローの使用はいかにも格好悪いし、いくらやりやすくなったからと言って意味のないドローン撮影も、時間経過、あるいは人物が内向する場面の緩さを音楽でごまかすのも勘弁してほしい(この点、本作に限らず)。
-
-
異人たち
-
文筆業
奈々村久生
主人公の内面世界と現実世界が渾然とした世界観。限られた登場人物と視点がその描写を可能にする。他者との関わりの少なさは自己の肥大を許し、それを妄想と呼ぶのは簡単だが、敢えてネタバレ前提で言うと(以下閲覧注意)「シックス・センス」のシステムをあくまでもドラマとして描いたのが大林宣彦版ともシャマランとも異なるところで、原作のエッセンスに近いかもしれない。愛の儚さと不確かさ、それにともなう孤独はヘイ監督のテーマでもあり、この世ならざる存在とは相性がよかったといえる。
-
アダルトビデオ監督
二村ヒトシ
最初ずいぶんスティーヴン・キングみがあるなと思ってたら劇中で言及されてた。〈甘える〉という魂に必要なことを人は大人になったらどこですればいいのさ。さみしさを癒そうとセックスすればするほどさみしくなるし、親と(その親が死んでても生きてても)コミュニケーションなんかしようものなら、ますますさみしくなる。自分は生きてると思ってる我々の営みはすべて、すでに死せる人たちが見ている夢なのだからさみしくてあたりまえだ。大林宣彦版に出た俳優さんたちはもうご覧になったかな。
-
映画評論家
真魚八重子
夕暮れのタワーマンションから見える、ロンドンの星々のような灯りの輝き。美しいと死にたくなる。大林の「異人たちとの夏」は、亡くなった両親が生きている息子の精気を吸い取るような奇妙な話だったが、本作は整頓されている。マンションに二人しか住人がおらず、クィアで美形なため惹かれあうのもわかるが、本作は薬物と強い酒が悲しく付きまとう。孤立したマンションで、訪ねるのも迎え入れるのも遅すぎた。クライマックスのトランス状態で時間が経過するのが上手い処理。
-
-
マンティコア 怪物
-
文筆業
奈々村久生
群青いろの新作「雨降って、ジ・エンド。」との相似が妙に腑に落ちる。カルロス・ベルムト監督ならではのトリッキーな作劇と抑制された語り口が効いていて、リアリズムではセンシティブになりすぎそうなところを絶妙なバランスで「表現」にスライドさせている。フィクションの矜持がうかがえるようなラストも見事。同じビターズ・エンド配給で昨年公開された「正欲」もテーマ的には同系譜に属しており、この題材は繰り返し描かれることによって、今後タブーから議論の対象になっていくと思う。
-
アダルトビデオ監督
二村ヒトシ
オタク男の妄想のモンスターがAIの暴走で実体化して悪さするホラーかと思ったら、そんな昔よくあった差別的な話じゃなくて、もっと地味な、つらい恋愛譚だった。異常な(って言いかたを僕はしたくないのだが)欲望をもってしまった者はどうやって幸せになればいいのか。日本の「怪物」は結果的にポリコレの人も反ポリコレの人もそれぞれが考えねばならないことを考えざるをえない映画になったわけだが、こっちの怪物にはできれば一生考えたくなかったことまで深く考えさせられてしまった。
-
映画評論家
真魚八重子
本作は主人公のとある秘密を隠して物語が進む。その核心に触れないように、話はずっと本題を避けた無駄話が続く。意図はわかるが、そのギミックに付き合わされる観客はたまったものではない。ある種の性的嗜好を持つ人々は、一生その欲望を経験できずに、妄想のままで終わらせなければならない。欲望を行動に移せば犯罪となり、その対象者に大きなトラウマを与えてしまう。それは確かに哀れであるが、もう一人の重要人物もいびつな共依存の欲望の持ち主で、ラストまで気持ち悪い。
-
-
氷室蓮司
-
ライター、編集
岡本敦史
破格の長期シリーズOV「日本統一」のスピンオフ。台湾ロケを敢行し、誘拐と爆弾テロと復讐劇をミックスした欲張りなドラマが展開するが、節約第一のOVテイストは健在。チープでけっこう、でも悪ふざけはしないという独特の美学は、作り手と常連客の信頼関係ありきのものなので、一見客には敷居の高い世界ではある。大陸におもねる経済ヤクザが登場したり、ひまわり学生運動がキーポイントになったり、独立系ならではの踏み込み方が面白い。80年代末の韓国にもこんな映画あった気が。
-
映画評論家
北川れい子
かつて一般向けの日本映画に背を向けるようにして、任?に生きる男たちやヤクザ世界の抗争などを描き、一部ファンに熱く支持されたVシネマ。当時とは世間も状況も激変したが、本作がその路線で踏ん張っていることに少なからず感心する。しかも今回はドラマ化もされている「日本統一」シリーズ10周年記念作品で舞台は台湾、チラッと台湾の歴史に触れたりも。日本統一を目指す侠和会のナンバー2、氷室の捨て身の父性愛で、話はいささか乱暴だが、それもVシネらしい。
-
映画評論家
吉田伊知郎
ひたすら本宮泰風を愛でてしまう。低温ながら俊敏な動きが際立ち、スター映画の残り香を漂わせる。「日本統一」シリーズが未見でも問題ない作りになっており、台湾を舞台に父子の物語へと拡張させても大味になることなく、ウエットにもならない。爆弾魔の話でありながら合成丸出しの爆発ばかりなのは不満だが、小気味良いアクションを積み重ねて終盤へなだれ込む手堅い演出は好調。東映系のシネコンチェーンで公開されるので、往年のプログラムピクチャーの味わいを愉しむのも一興。
-
-
プリシラ(2023)
-
俳優
小川あん
エルヴィス・プレスリーと初妻プリシラの出会い・結婚・離別までを描く。時系列どおりのノーマルな物語構成。特筆すべきシーンはないのだが、S・コッポラの得意なガールズ・ムービーとしての画作りは深まっている。プリシラの少女性と同時にエルヴィスの少年性が見えたのは新たな発見だった。二人の恋路を眺めていると、エルヴィスに恋をしたような気持ちにさせてくれる。ただ、個人的にバズ・ラーマン監督作「エルヴィス」が前に出てしまったので、本作の印象が少し薄くなってしまった。
-
翻訳者、映画批評
篠儀直子
少女プリシラが飛びこむ状況の異様さは傍から見れば一目瞭然。最初は夢見心地でも、王子様だったエルヴィスはやがて精神的な不安定さゆえに支配欲をむき出しに。女性の自立や尊厳がまだほとんど問題にすらされていなかった時代、彼女はファーストショットで示されたように、自分の足でしっかりと歩けるようになるのだろうか?という話に着地するはずだと思うのだが、最終的にふわっとしてしまうのは、まあソフィアのよさでもあるのだろう。プレスリーの曲がほぼ流れないのも興味深い。
-
編集者/東北芸術工科大学教授
菅付雅信
エルヴィス・プレスリーの元妻プリシラのエルヴィスとの日々を彼女の回顧録をもとにソフィア・コッポラが映画化。保守的な家庭で育った少女プリシラが偶然エルヴィスと出会い、求愛を受けて結婚しスーパースターの華美な館で「籠の中の鳥」のような日々を送る。映画はプリシラの視点で作られ、彼女の「物質的に満たされた空虚さ」を執拗なディテール描写で描く。ソフィア十八番の「お姫様の憂鬱」話だが、もうソフィアの憂鬱ゴッコにうんざり。この空虚さから脱しないと映画作家としてヤバいのでは。
-
-
No.10
-
映画監督
清原惟
始めと終わりで全く別の映画のように、悪夢のようにさまざまなジャンルを横断していく。とある舞台の座組みの中で起きているドロドロした人間関係の話だと思って観ていると、途中からサスペンスのような雰囲気になり、と思えば最後は異星人SFものになっていた。しかし、すべてに冗談めいた空気があるからか、ジャンルの移り変わりをすんなり受け入れて観られたのが奇妙だった。スケールの大きな話なのにも拘らず、登場人物が最初からあまり変わらず、どこかスモールワールド的な雰囲気も。
-