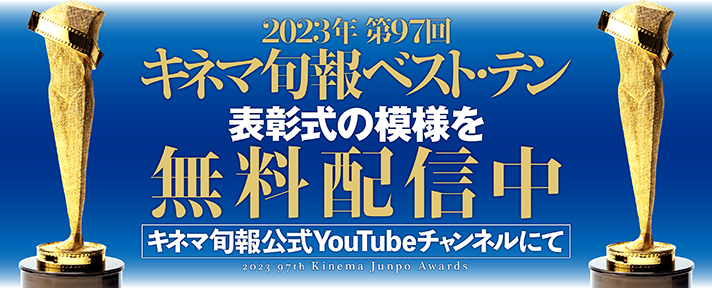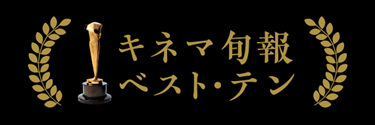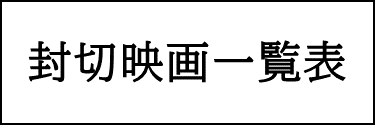「伊豆の踊子(1974)」のストーリー
大正の末、天城に向かう山道を行く一高生・川島は、旅芸人の一行に出会った。一行は栄吉とその妻・千代子、千代子の母親ののぶ、雇い娘の百合子、そして太鼓を背負った古風な髪型のよく似合う美しい少女の五人で、彼らは三味線や太鼓、そして唄や踊りで温泉場の料理屋や旅館の客を相手につつましい生計をたてていた。かおるという名のその踊子は、下田まで川島と一緒に旅ができると知って喜んだ。湯ケ野について踊子と五目並べに興じていたある日、栄吉と風呂に入っていた川島は、向かいの共同風呂に入っていた踊子が裸のまま立ち上り、こちらに手を振るのを見てその無邪気な子供らしさに思わず頬笑んだ。そんなある日、踊子は山蔭の古小屋で、粗末な夜具にくるまって寝ている幼馴じみのおきみと再会した。酌婦をしていたおきみは客を取らされ、病気になった今は、厄病神あつかいされて古小屋に追い払われていたのだった。浮世の汚れを知らぬ踊子には余りにも衝撃的な光景であった。やがておきみの死を知ることなく湯ケ野を離れた踊子一行は、川島と共に下田へ向かった。踊子は、道中ずっと生まれ故郷の甲府のことや、今住んでいる大島のことを川島に話して聞かせた。踊子のはずむような声が川島の胸に心地よく響いた。下田に着いて、明日は川島が東京へ帰るという日、川島との活動見物を楽しみにしていた踊子は、二人の仲を案じたのぶに止められて涙を呑んだ。翌朝、川島が栄吉に送られて乗船場に近づくと、海辺に踊子の姿があった。つかの間の別れを告げ、川島の乗ったはしけが遠ざかり、大きく曲って岬のかげに隠れた。踊子は栄吉が止めるのも聞かずに走った。岬の突端へ出ると、巡航船に乗り移ろうとする川島の姿が見えた。思いきり手を振る踊子。彼女に気づいた川島も、甲板の上から狂ったように手を振る。船が動き出し次第に小さくなっていくかおるの姿。あふれる涙をぬぐいもせず手を振りつづけている川島の手には、ついさっき踊子からもらった櫛が握られていた。岬はもう、見えない……。