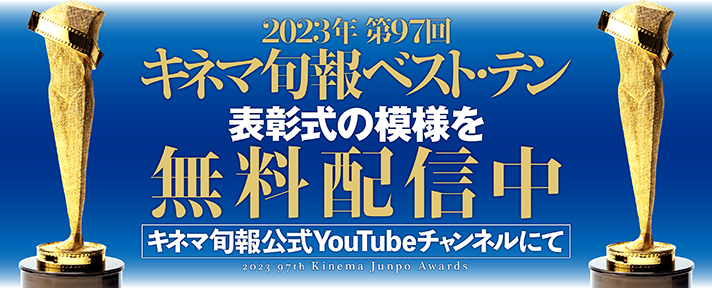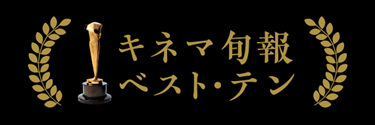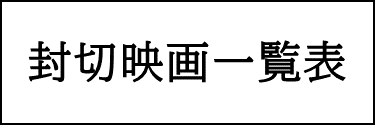「火の夜」のストーリー
一九〇四年、聖ペテルスブルグの冬であった。暗い灰色の中空に厳としてそびえ立つ裁判所の大架堂では、嫉妬から愛する妻を殺した若い殺人犯の公判が開かれた。弁護士は今巣立ったばかりの青年セルジュ・イヴァノヴィッチ、検事はセルジュが兄として親み師として敬うフェドール・アンドレイエフである。法廷では激しく論争しても、私生活では肉親の様な間柄だった。傍聴席にはフェドールの美しい妻リーザの姿も見えた。彼女は幼馴染のセルジュの初陣を気にして此処へ来たのであった。その席でフェドールは、ふと裁判所の代理人ボビニーヌが誠しやかにセルジュとリーザの間を書記に囁くのを聞いた。二人を信じていてもフェドールには何かそれは気懸かりだった。その夜彼は妻とセルジュを先に劇場へやって、自分はシベリヤへ終身刑を宣告された今日の殺人犯を訪れた。若い犯人は「妻は男を愛していました、思えば私は余計な存在だったにすぎません」と嘆くのであった。遅れて劇場へ着いたフェドールは妻とセルジュの親しげな様子を見て更に不安の念を強めた。バレエ「火の夜」を見て馬車で帰路についた三人は、ネバ河の畔で車を止め霧の中を散歩した。突如フェドールは疑惑を制し切れずセルジュを捉えて激しい言葉を浴びせた。やがて馬車へ帰ったのはセルジュとリーザの二人だけだった。フェドールは一人ジプシイの酒場へ行って、密室で遺書を書き自殺しようと計ったが、ジプシイ女マーシャに止められて果たさなかった。しかし翌朝ネバ河畔にフェドールの外套とリーザ宛の手紙が発見され、やがて顔の見判けもつかぬ死体が見つかった。こうしてフェドール・アンドレイエフの名は消え去ったのである。リーザは世間の噂を裏切ってセルジュとも結婚せず、亡き夫の愛情をしのびながら憂き多き毎日を送っていた。警察では彼女に夫殺しの嫌疑をかけ、次々と現れる証人や証拠の品によって殆ど有罪は免れないようであった。リーザは一年前に死んだフェドールの愛情が如何に深かったか、また自分がどれほど彼を愛していたかが今更のように解るのだった。その頃某国との戦いに前線に出動しているロシア軍の中に、ピョートル・イグナトフと云う勇敢な兵士があった。彼は塹壕の中で見た新聞でリーザが夫殺しの罪で裁かれている事を知った。イグナトフこそは一年前に死んだ筈のフェドールだった。首都ではリーザの罪は、最後の夜に三人を乗せた馭者の証言で殆ど決定的なものとなって、検事に昇進したボビニーヌが宣告しようとした時、法廷に現れたのは兵士イグナトフだった。彼はあの夜追い剥ぎに襲われた所をマーシャに助けられてから今日迄の事を話した。直ちに告訴は却下となり、再び戦線へ戻るフェドールに、リーザは心からの愛を告白し、何時までも待っていると云うのであった。